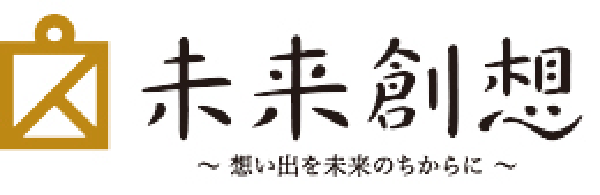終活に関する記事

「終活はいつから始める?」後悔しない終活のすすめ方
人生の締めくくりについて考え始めたとき、「終活はいつごろから始めたらいいだろう?」そんな疑問を持つ方も多いことでしょう。この記事では、終活を始めるタイミングや、終活のポイントを伝授。今、関心が高まっている、手元供養についてもあわせてご紹介いたします。 終活はいつから始めるのがベスト? 人生の終わりについて意識をする年齢になったとき、もしくは身近な誰かが亡くなるといった経験が、終活を始めるきっかけとなる人も多いのではないでしょうか? さまざまなリサーチを行う楽天インサイト株式会社 は、全国の20代から60代の男女1000人を対象に、終活に関する調査を実施。 終活をいつから始めたいかの問いに対しては、「60代」と答えた人が全体の40%以上を占めました。 終活をする主な理由としては、 家族に迷惑をかけたくないから(71.4%) 病気や怪我、介護生活で寝たきりになった場合に備えるため(48.6%) 葬儀などの希望を家族に伝えるため(38.9%) この3つが上位に。 男女によっても意識に違いが 終活に対する意識については、終活という言葉を聞いたことがある人が、全体の96.6%いるのに対し、終活の意向がある人は全体の39.1%という結果に。 さらに終活の意向があると答えた中では、男性の割合が41.4%、女性の割合が58.6%と、女性のほうが意識が高いということが分かりました。平均寿命が男性よりも長い女性ならではの、老後への心配が伺える結果とも言えるでしょう。 この調査では、半数近くが終活の意向を示す一方で、実際に終活を実施しているのはたったの1割という結果も出ています。 いざというときに十分な終活ができていなかったと後悔する前に、関心を持ち始めたタイミングで、早めに終活を始めることが望まれます。そのメリットについても、少し触れておきましょう。 終活をしておくメリット まずはお金のことについて。人生の終末期にかかる費用のことを、終活でしっかりと計画しておくことで、無駄な出費を省くことができます。 老後を楽しむために使えるお金についても明確になりますし、より多くのお金を残すこともできるでしょう。 また、延命治療や葬儀といったデリケートな問題は、実際にそのときが近くなるとなかなか口にしづらいといった面もありますので、明確にしておくと安心です。 このように終活をしておくことで安心感が生まれ、残された人生をより前向きに充実して過ごすことができるのです。 終活で押さえておきたい3つのポイント ではここで、終活を進める上で押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。 主にこの3つを中心に準備をしておくと安心です。 1.エンディングノート 家族や知人に伝えておきたいことを記しておくノートのこと。人生の終末期における自身の希望や、遺産相続にいたるまで、心残りのないようにつづっておきましょう。 書店の終活コーナーなどで販売をしているエンディングノートなら、必要な項目が記載されていて、効率的に書きすすめることができるのでおすすめです。 2.所有物等の身の回りの整理 身の回りの物品の整理や、財産に関わる所有物等の整理をしておきます。特に遺産相続に関することは、明確にしておくことが大切です。 3.葬儀やお墓について...
「終活はいつから始める?」後悔しない終活のすすめ方
人生の締めくくりについて考え始めたとき、「終活はいつごろから始めたらいいだろう?」そんな疑問を持つ方も多いことでしょう。この記事では、終活を始めるタイミングや、終活のポイントを伝授。今、関心が高まっている、手元供養についてもあわせてご紹介いたします。 終活はいつから始めるのがベスト? 人生の終わりについて意識をする年齢になったとき、もしくは身近な誰かが亡くなるといった経験が、終活を始めるきっかけとなる人も多いのではないでしょうか? さまざまなリサーチを行う楽天インサイト株式会社 は、全国の20代から60代の男女1000人を対象に、終活に関する調査を実施。 終活をいつから始めたいかの問いに対しては、「60代」と答えた人が全体の40%以上を占めました。 終活をする主な理由としては、 家族に迷惑をかけたくないから(71.4%) 病気や怪我、介護生活で寝たきりになった場合に備えるため(48.6%) 葬儀などの希望を家族に伝えるため(38.9%) この3つが上位に。 男女によっても意識に違いが 終活に対する意識については、終活という言葉を聞いたことがある人が、全体の96.6%いるのに対し、終活の意向がある人は全体の39.1%という結果に。 さらに終活の意向があると答えた中では、男性の割合が41.4%、女性の割合が58.6%と、女性のほうが意識が高いということが分かりました。平均寿命が男性よりも長い女性ならではの、老後への心配が伺える結果とも言えるでしょう。 この調査では、半数近くが終活の意向を示す一方で、実際に終活を実施しているのはたったの1割という結果も出ています。 いざというときに十分な終活ができていなかったと後悔する前に、関心を持ち始めたタイミングで、早めに終活を始めることが望まれます。そのメリットについても、少し触れておきましょう。 終活をしておくメリット まずはお金のことについて。人生の終末期にかかる費用のことを、終活でしっかりと計画しておくことで、無駄な出費を省くことができます。 老後を楽しむために使えるお金についても明確になりますし、より多くのお金を残すこともできるでしょう。 また、延命治療や葬儀といったデリケートな問題は、実際にそのときが近くなるとなかなか口にしづらいといった面もありますので、明確にしておくと安心です。 このように終活をしておくことで安心感が生まれ、残された人生をより前向きに充実して過ごすことができるのです。 終活で押さえておきたい3つのポイント ではここで、終活を進める上で押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。 主にこの3つを中心に準備をしておくと安心です。 1.エンディングノート 家族や知人に伝えておきたいことを記しておくノートのこと。人生の終末期における自身の希望や、遺産相続にいたるまで、心残りのないようにつづっておきましょう。 書店の終活コーナーなどで販売をしているエンディングノートなら、必要な項目が記載されていて、効率的に書きすすめることができるのでおすすめです。 2.所有物等の身の回りの整理 身の回りの物品の整理や、財産に関わる所有物等の整理をしておきます。特に遺産相続に関することは、明確にしておくことが大切です。 3.葬儀やお墓について...

生前葬についての疑問にお答えします!
“生きているうちに、お世話になった方々に直接お礼の気持ちを伝えたい”そんな思いをかたちにした、「生前葬」に関心が高まりつつあります。「生前葬って実際にはどうなんだろう?」「どのように執り行うの?」「生前葬に招かれたけどどうすればいい?」ここでは、そんな生前葬にまつわる疑問にお答えします。 生前葬とは? 生前葬はその言葉からも想像ができるように、本人が生きている間に執り行う葬儀のこと。“人生の中でお世話になった大切な方々へ、直接会ってお礼の気持ちを伝えたい”そんな思いから生まれた、葬儀の新しいスタイルです。 では実際に行われている生前葬の、一般的な内容を少しご紹介いたします。 実際に行われている生前葬の内容(例) 主催者のあいさつ 親しい方からのスピーチ 食事や歓談 人生を振り返るスライドショーなどの上映 ビンゴやカラオケ、生演奏などの余興 プレゼントや花束等の贈呈 招待客に会葬のお礼 このように生前葬は、形式的な一般の葬儀と比べると、とても自由度が高いことが分かると思います。生前葬についてのメリットも見てみましょう。 生前葬のメリット 生前葬の一番のメリットは、何といっても人生でお世話になった方への感謝の気持ちを、本人から直接伝えることができる点です。一般的な葬儀と比べるととても自由度が高く、自分の思い描く葬儀ができます。 かかる費用についても、ある程度自分の考えで決められる点がメリット。「お別れは自分らしく」そう思う方にとっては、とてもよい方法と言えるでしょう。 しかし一方で、まだまだ一般的な葬儀としては浸透していないのも事実ですので、実際に生前葬を執り行うとなると、細かな配慮が必要です。 生前葬を執り行う際の注意点 前例の少ない生前葬ですので、まずは家族としっかり話し合いをして、理解を得ておくことが大切です。 細かな段取りについては、生前葬の相談を受け付けている葬祭場に相談してみるのもひとつの方法。しっかりと計画をして、招待される側が戸惑わないよう、細かな配慮をする必要があります。 また、生前葬を済ませたからと言って、やるべきことがすべて終わったわけではありません。実際に亡くなったあと、家族葬をする場合もありますし、葬儀を行わない場合でも、納棺、出棺、火葬、お骨上げは必ず必要となることを心に留めておきましょう。 生前葬に招かれたときのマナーについて ここまでは、生前葬を行う際の注意点についてご紹介をしましたが、招かれた際のマナーについても、少し触れておきます。 まずは香典について。生前葬は会費制であることが多く、会費制であった場合は香典を準備する必要はないでしょう。 会費制ではなく、香典も辞退する旨が伝えられている場合は、後日お手紙などを添えて品物を贈るのもひとつの方法です。 いずれの記載もない場合は、本人に確認をするか、もしくは同じく招待をされている人と相談をして決めるとよいでしょう。生前葬の香典は、おおよそ1万〜2万円くらいが相場です。 服装については、指定のドレスコードに従いますが、記載がない場合は香典と同じく、主催者や参列者に相談してみるとよいでしょう。「平服で」と記載があった場合は、ワンピースやスーツなどがおすすめです。 生前葬とあわせて考えておきたい供養方法の種類 生前葬を検討する際、さらに一歩進んで考えておきたいのが供養方法です。 火葬をしたあと、自分がどのように供養をしてもらいたいか、事前に伝えておくことが大切です。一般的なお墓への納骨だけではなく、いろいろな供養方法がありますので少しご紹介します。...
生前葬についての疑問にお答えします!
“生きているうちに、お世話になった方々に直接お礼の気持ちを伝えたい”そんな思いをかたちにした、「生前葬」に関心が高まりつつあります。「生前葬って実際にはどうなんだろう?」「どのように執り行うの?」「生前葬に招かれたけどどうすればいい?」ここでは、そんな生前葬にまつわる疑問にお答えします。 生前葬とは? 生前葬はその言葉からも想像ができるように、本人が生きている間に執り行う葬儀のこと。“人生の中でお世話になった大切な方々へ、直接会ってお礼の気持ちを伝えたい”そんな思いから生まれた、葬儀の新しいスタイルです。 では実際に行われている生前葬の、一般的な内容を少しご紹介いたします。 実際に行われている生前葬の内容(例) 主催者のあいさつ 親しい方からのスピーチ 食事や歓談 人生を振り返るスライドショーなどの上映 ビンゴやカラオケ、生演奏などの余興 プレゼントや花束等の贈呈 招待客に会葬のお礼 このように生前葬は、形式的な一般の葬儀と比べると、とても自由度が高いことが分かると思います。生前葬についてのメリットも見てみましょう。 生前葬のメリット 生前葬の一番のメリットは、何といっても人生でお世話になった方への感謝の気持ちを、本人から直接伝えることができる点です。一般的な葬儀と比べるととても自由度が高く、自分の思い描く葬儀ができます。 かかる費用についても、ある程度自分の考えで決められる点がメリット。「お別れは自分らしく」そう思う方にとっては、とてもよい方法と言えるでしょう。 しかし一方で、まだまだ一般的な葬儀としては浸透していないのも事実ですので、実際に生前葬を執り行うとなると、細かな配慮が必要です。 生前葬を執り行う際の注意点 前例の少ない生前葬ですので、まずは家族としっかり話し合いをして、理解を得ておくことが大切です。 細かな段取りについては、生前葬の相談を受け付けている葬祭場に相談してみるのもひとつの方法。しっかりと計画をして、招待される側が戸惑わないよう、細かな配慮をする必要があります。 また、生前葬を済ませたからと言って、やるべきことがすべて終わったわけではありません。実際に亡くなったあと、家族葬をする場合もありますし、葬儀を行わない場合でも、納棺、出棺、火葬、お骨上げは必ず必要となることを心に留めておきましょう。 生前葬に招かれたときのマナーについて ここまでは、生前葬を行う際の注意点についてご紹介をしましたが、招かれた際のマナーについても、少し触れておきます。 まずは香典について。生前葬は会費制であることが多く、会費制であった場合は香典を準備する必要はないでしょう。 会費制ではなく、香典も辞退する旨が伝えられている場合は、後日お手紙などを添えて品物を贈るのもひとつの方法です。 いずれの記載もない場合は、本人に確認をするか、もしくは同じく招待をされている人と相談をして決めるとよいでしょう。生前葬の香典は、おおよそ1万〜2万円くらいが相場です。 服装については、指定のドレスコードに従いますが、記載がない場合は香典と同じく、主催者や参列者に相談してみるとよいでしょう。「平服で」と記載があった場合は、ワンピースやスーツなどがおすすめです。 生前葬とあわせて考えておきたい供養方法の種類 生前葬を検討する際、さらに一歩進んで考えておきたいのが供養方法です。 火葬をしたあと、自分がどのように供養をしてもらいたいか、事前に伝えておくことが大切です。一般的なお墓への納骨だけではなく、いろいろな供養方法がありますので少しご紹介します。...

自分らしい終わり方を描く「終活」とは?
昨今、「終活」という言葉を耳にすることが多くなってきました。しかし、終活について詳しい内容まではご存知ない方も多いのではないでしょうか。終活とは、人生の終わりに向けての活動や準備のことを言い、人生の最後をより良いかたちにするためのものです。 そこで今回は、終活とは何か、どんな準備をしておけば良いのかといった項目についてご紹介します。「自分らしい人生の終わり方を描く」ための一歩目として、終活について見ていきましょう。 終活とは? 終活(しゅうかつ)とは、生前から、人生の終わりに向けての活動や準備をすることを言います。 これまでも、生前整理や遺産相続といった活動は行われてきましたが、近年の終活では「最後までより良い人生を送る」ことを目的として、さまざまな準備を行うケースが多いようです。 今、どうして終活なのか? では、どうしてこれほどまで終活が注目を集めているのでしょうか? 一つ目の理由は医療水準が高まったことで、平均寿命が長くなったため。 厚生労働省による調査では、2017年の日本の平均寿命は女性が87.26歳、男性81.09歳となっています。これは1990年と比較しても男女ともに約5歳以上も長くなっている計算です(1990年:女性81.90歳、男性75.92歳)。 平均寿命が長くなるということは、それだけ亡くなるまでの期間も長くなるということ。この期間をより有意義に、充実したものとすることが、終活が注目を集める一つ目の理由です。 二つ目は、価値観が多様化してきたということ。 時代の変化とともに、私たちの価値観も多様化してきました。より自分らしい人生の終わりを望む人も増えており、こうした価値観の変化も終活が注目される理由のひとつでしょう。 終活でしておくべき3つのこと それでは、終活を行う際には具体的にどんなことをしておくべきなのでしょうか?ここでは、特に大切な3つのポイントをご紹介します。 1.葬儀 終活でしておくべきことの一つ目は、葬儀です。 なかでも、葬儀の費用については、しっかりと検討しておく必要があるでしょう。最近ではお葬式を行う場所も多様化してきました。それに合わせて、どの葬儀場が良いのか迷ってしまうケースも増えています。 とくにパックプランや割安な料金を売りにしている場合は、オプションなどの項目も確認しておくことが大切です。 ご自身がどんな葬儀を行いたいのかまず整理し、具体的に葬儀には何が必要か・必要でないのかを確認しておきましょう。 また、葬儀は悲しみや混乱の中で行わなければならず、残されたご遺族にとって負担の大きいものです。生前に家族と葬儀について話し合っておくのも、大切な終活のひとつです。 2.お墓 お墓について考えることも、終活ではとても大切なことです。 一口にお墓と言っても、さまざまな種類があります。お寺や霊園のお墓はもちろん、納骨堂や手元供養もお墓を考えるうえでは欠かせません。自分がどんなお墓で眠るのが理想なのかをまず考えてみましょう。 また、お墓の管理への負担や、家族がどこで暮らしているのかを検討材料に加えておくことも大事なことです。 3.仏壇 仏壇についても、終活の中で考えておくべき項目のひとつです。 マンションなどの集合住宅に住むことが多い現代では、一戸建てなどの住宅に比べ、自宅のスペースが狭くなる傾向にあります。そのため、仏壇を選ぶ際はサイズをよく検討しておく必要があるでしょう。 仏壇の大小だけでなく、「ご遺族との距離を近く感じるためには」という視点に立って選んでみるのも、より良い仏壇選びにつながります。 手元供養って何? みなさんは「手元供養(てもとくよう)」という言葉をご存知でしょうか?...
自分らしい終わり方を描く「終活」とは?
昨今、「終活」という言葉を耳にすることが多くなってきました。しかし、終活について詳しい内容まではご存知ない方も多いのではないでしょうか。終活とは、人生の終わりに向けての活動や準備のことを言い、人生の最後をより良いかたちにするためのものです。 そこで今回は、終活とは何か、どんな準備をしておけば良いのかといった項目についてご紹介します。「自分らしい人生の終わり方を描く」ための一歩目として、終活について見ていきましょう。 終活とは? 終活(しゅうかつ)とは、生前から、人生の終わりに向けての活動や準備をすることを言います。 これまでも、生前整理や遺産相続といった活動は行われてきましたが、近年の終活では「最後までより良い人生を送る」ことを目的として、さまざまな準備を行うケースが多いようです。 今、どうして終活なのか? では、どうしてこれほどまで終活が注目を集めているのでしょうか? 一つ目の理由は医療水準が高まったことで、平均寿命が長くなったため。 厚生労働省による調査では、2017年の日本の平均寿命は女性が87.26歳、男性81.09歳となっています。これは1990年と比較しても男女ともに約5歳以上も長くなっている計算です(1990年:女性81.90歳、男性75.92歳)。 平均寿命が長くなるということは、それだけ亡くなるまでの期間も長くなるということ。この期間をより有意義に、充実したものとすることが、終活が注目を集める一つ目の理由です。 二つ目は、価値観が多様化してきたということ。 時代の変化とともに、私たちの価値観も多様化してきました。より自分らしい人生の終わりを望む人も増えており、こうした価値観の変化も終活が注目される理由のひとつでしょう。 終活でしておくべき3つのこと それでは、終活を行う際には具体的にどんなことをしておくべきなのでしょうか?ここでは、特に大切な3つのポイントをご紹介します。 1.葬儀 終活でしておくべきことの一つ目は、葬儀です。 なかでも、葬儀の費用については、しっかりと検討しておく必要があるでしょう。最近ではお葬式を行う場所も多様化してきました。それに合わせて、どの葬儀場が良いのか迷ってしまうケースも増えています。 とくにパックプランや割安な料金を売りにしている場合は、オプションなどの項目も確認しておくことが大切です。 ご自身がどんな葬儀を行いたいのかまず整理し、具体的に葬儀には何が必要か・必要でないのかを確認しておきましょう。 また、葬儀は悲しみや混乱の中で行わなければならず、残されたご遺族にとって負担の大きいものです。生前に家族と葬儀について話し合っておくのも、大切な終活のひとつです。 2.お墓 お墓について考えることも、終活ではとても大切なことです。 一口にお墓と言っても、さまざまな種類があります。お寺や霊園のお墓はもちろん、納骨堂や手元供養もお墓を考えるうえでは欠かせません。自分がどんなお墓で眠るのが理想なのかをまず考えてみましょう。 また、お墓の管理への負担や、家族がどこで暮らしているのかを検討材料に加えておくことも大事なことです。 3.仏壇 仏壇についても、終活の中で考えておくべき項目のひとつです。 マンションなどの集合住宅に住むことが多い現代では、一戸建てなどの住宅に比べ、自宅のスペースが狭くなる傾向にあります。そのため、仏壇を選ぶ際はサイズをよく検討しておく必要があるでしょう。 仏壇の大小だけでなく、「ご遺族との距離を近く感じるためには」という視点に立って選んでみるのも、より良い仏壇選びにつながります。 手元供養って何? みなさんは「手元供養(てもとくよう)」という言葉をご存知でしょうか?...