分骨に関する記事
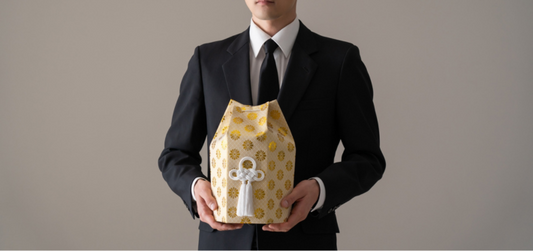
直葬・火葬式とは?火葬後の供養の仕方についても詳しく紹介
直葬・火葬式とは、亡くなった後、お通夜や葬儀などを行わずに火葬のみで済ませる葬儀の形式をいいます。一連の葬儀の儀式にかける時間や費用を減らせるメリットがありますが、比較的新しい葬儀のやり方のため、正確な情報を知らない人も多いでしょう。 本記事では、直葬・火葬式のメリット・デメリットや注意点について詳しく解説するとともに、直葬・火葬後の流れなども紹介します。 直葬・火葬式とは 直葬・火葬式とは、お通夜や告別式などを行わずに、火葬だけで済ませる葬儀の形式です。一般的には人が亡くなるとお通夜、告別式や葬儀などを執り行いその後火葬する流れになりますが、直葬・火葬式の場合はそのまま火葬するため、一連の葬儀に関する準備や時間、費用などを大幅にカットできます。 直葬・火葬式は比較的新しい葬儀形式で、まだあまり馴染みがない方も少なくありません。 直葬・火葬式の違い 一言で「直葬・火葬式」といっても、詳細は少し異なります。直葬は宗教的な儀式を執り行わず、火葬のみで済ませることをいい、火葬式は宗教的儀式を伴う葬儀が基本となっています。 直葬は先ほどもお伝えしたとおり宗教的な儀式を執り行わないこと、そしてごく近しい身内のみで執り行われ、火葬後の「骨上げ」のみを行います。次に火葬式は、基本的には僧侶を呼んで火葬の間に読経供養が行われます。そのため、お布施の準備が必要な可能性がありますので覚えておきましょう。 直葬・火葬式にかかる費用 直葬・火葬式にかかる費用を見ていきましょう。一般的な葬儀や家族葬などと比較してみます。 葬儀の平均費用総額 一般的に多い価格帯 一般の葬儀 161.3万円 120万円~140万円未満 家族葬 105.7万円 60万円~80万円未満 一日葬 87.5万円 20万円~40万円未満 直葬・火葬式 42.8万円 20万円~40万円未満 一般的な葬儀の費用総額が161.3万円であるのに対し、直葬・火葬式の場合は42.8万円と約4分の1ほどの費用で済みます。(1) 直葬・火葬式が増えている理由 直葬・火葬式は比較的新しい葬儀の形ですが、近年は直葬・火葬式を選ぶ人が増えています。経済的に困っている人が選ぶだけではなく、葬儀にお金をかけたくないと考える人や家族や周りに負担をかけたくない人などが直葬・火葬式での葬儀を希望しています。 お葬式に関する全国調査(2024年)によると、家族葬が50.0%、一般葬が30.1%、一日葬が10.2%、直葬・火葬式が9.6%という割合でした。一日葬と直葬・火葬式はほとんど変わらない数字となっていました。 直葬・火葬式が増えている背景には、自由な終活が浸透してきたことや、核家族や生涯独身の人が増えてきたことなども関係しています。...
直葬・火葬式とは?火葬後の供養の仕方についても詳しく紹介
直葬・火葬式とは、亡くなった後、お通夜や葬儀などを行わずに火葬のみで済ませる葬儀の形式をいいます。一連の葬儀の儀式にかける時間や費用を減らせるメリットがありますが、比較的新しい葬儀のやり方のため、正確な情報を知らない人も多いでしょう。 本記事では、直葬・火葬式のメリット・デメリットや注意点について詳しく解説するとともに、直葬・火葬後の流れなども紹介します。 直葬・火葬式とは 直葬・火葬式とは、お通夜や告別式などを行わずに、火葬だけで済ませる葬儀の形式です。一般的には人が亡くなるとお通夜、告別式や葬儀などを執り行いその後火葬する流れになりますが、直葬・火葬式の場合はそのまま火葬するため、一連の葬儀に関する準備や時間、費用などを大幅にカットできます。 直葬・火葬式は比較的新しい葬儀形式で、まだあまり馴染みがない方も少なくありません。 直葬・火葬式の違い 一言で「直葬・火葬式」といっても、詳細は少し異なります。直葬は宗教的な儀式を執り行わず、火葬のみで済ませることをいい、火葬式は宗教的儀式を伴う葬儀が基本となっています。 直葬は先ほどもお伝えしたとおり宗教的な儀式を執り行わないこと、そしてごく近しい身内のみで執り行われ、火葬後の「骨上げ」のみを行います。次に火葬式は、基本的には僧侶を呼んで火葬の間に読経供養が行われます。そのため、お布施の準備が必要な可能性がありますので覚えておきましょう。 直葬・火葬式にかかる費用 直葬・火葬式にかかる費用を見ていきましょう。一般的な葬儀や家族葬などと比較してみます。 葬儀の平均費用総額 一般的に多い価格帯 一般の葬儀 161.3万円 120万円~140万円未満 家族葬 105.7万円 60万円~80万円未満 一日葬 87.5万円 20万円~40万円未満 直葬・火葬式 42.8万円 20万円~40万円未満 一般的な葬儀の費用総額が161.3万円であるのに対し、直葬・火葬式の場合は42.8万円と約4分の1ほどの費用で済みます。(1) 直葬・火葬式が増えている理由 直葬・火葬式は比較的新しい葬儀の形ですが、近年は直葬・火葬式を選ぶ人が増えています。経済的に困っている人が選ぶだけではなく、葬儀にお金をかけたくないと考える人や家族や周りに負担をかけたくない人などが直葬・火葬式での葬儀を希望しています。 お葬式に関する全国調査(2024年)によると、家族葬が50.0%、一般葬が30.1%、一日葬が10.2%、直葬・火葬式が9.6%という割合でした。一日葬と直葬・火葬式はほとんど変わらない数字となっていました。 直葬・火葬式が増えている背景には、自由な終活が浸透してきたことや、核家族や生涯独身の人が増えてきたことなども関係しています。...

分骨用骨壷、ちょうどいいサイズを選ぶには?2寸〜5寸まで幅広いサイズをご紹介
分骨するときに必要な骨壷。どれくらいのサイズがいいのか、大きさはなにを基準に選べばいいのかをまとめました。せっかくの分骨ですから、ちょうどいいサイズのものをうまく選びましょう。 伝統的な分骨用骨壷 西日本では火葬時に分骨をし、本山納骨をする習慣が古くからあります。そのため、現在でも火葬の際に分骨用の骨壷が準備されることも。分骨用の骨壷には喉仏を入れるのが一般的で、ほとんどが2寸〜3寸のサイズです。 筒状の骨壷の場合、2寸は高さが約7.5cm・ 直径が約6.5cm、3寸になると高さが約11cm・直径が約9.5cmという大きさ。少量の御遺骨を納めるには、2〜3寸サイズの骨壷で十分と考えられます。 手元供養ならもっと小さいサイズから展開 自宅で手元供養するための骨壷であれば、2寸、3寸よりももっとコンパクトな骨壷を選んでも問題ありません。部屋のインテリアや置く場所などに合わせて好みのサイズやデザインを選びましょう。 また、小さいサイズの骨壷は、ペット用の骨壷として使われることもあります。人間の遺骨よりも小さいペットの遺骨なら、分骨用の骨壷のサイズにぴったりです。飼っていたペットの大きさにもよりますが、2寸〜3寸のサイズの骨壷ならペットの全骨を納めて家で供養できます。 ペットは家族の一員なので、全骨を骨壷に納めて手元に置いておきたいと考える方もいるでしょう。手元供養向けの骨壷の中には、おしゃれなものも多いので、愛するペットの遺骨を入れて毎日家で供養する方も少なくありません。 一般的な骨壷のサイズ 一般的な骨壷のサイズは、小さい骨壷は2寸、大きいものなら尺寸までサイズがさまざまあります。骨壷に使われる「寸」という単位は、骨壺のサイズを表しており、一寸は3.03cmです。一番大きな骨壷の尺寸は、直径が31.5cmになります。 納骨に使われる骨壷は、5寸〜7寸のものが多く、関東と関西で用いられる骨壷のサイズは、関東は7寸、関西では6寸と若干異なります。これは、関東では火葬の後、すべての遺骨を納めるのに対し、関西では喉仏など一部の遺骨しか拾骨しないためです。 また、近年注目を浴びている手元供養に用いられる骨壷は2寸と小さいサイズが主流です。骨壷のサイズは全部で9種類あり、それぞれの大きさは次の通りです。 骨壷の大きさ 縦横のサイズ 2寸 直径約6.5㎝×高さ約7.5㎝ 2.3寸 直径約7.0㎝×高さ約8.5㎝ 3寸 直径約9.5㎝×高さ約11.0㎝ 4寸 直径約12.5㎝×高さ約14.0㎝ 5寸 直径約15.5㎝×高さ約17.5㎝ 6寸 直径約18.0㎝×高さ約20.5㎝ 7寸 直径約22.0㎝×高さ約25.5㎝ 8寸...
分骨用骨壷、ちょうどいいサイズを選ぶには?2寸〜5寸まで幅広いサイズをご紹介
分骨するときに必要な骨壷。どれくらいのサイズがいいのか、大きさはなにを基準に選べばいいのかをまとめました。せっかくの分骨ですから、ちょうどいいサイズのものをうまく選びましょう。 伝統的な分骨用骨壷 西日本では火葬時に分骨をし、本山納骨をする習慣が古くからあります。そのため、現在でも火葬の際に分骨用の骨壷が準備されることも。分骨用の骨壷には喉仏を入れるのが一般的で、ほとんどが2寸〜3寸のサイズです。 筒状の骨壷の場合、2寸は高さが約7.5cm・ 直径が約6.5cm、3寸になると高さが約11cm・直径が約9.5cmという大きさ。少量の御遺骨を納めるには、2〜3寸サイズの骨壷で十分と考えられます。 手元供養ならもっと小さいサイズから展開 自宅で手元供養するための骨壷であれば、2寸、3寸よりももっとコンパクトな骨壷を選んでも問題ありません。部屋のインテリアや置く場所などに合わせて好みのサイズやデザインを選びましょう。 また、小さいサイズの骨壷は、ペット用の骨壷として使われることもあります。人間の遺骨よりも小さいペットの遺骨なら、分骨用の骨壷のサイズにぴったりです。飼っていたペットの大きさにもよりますが、2寸〜3寸のサイズの骨壷ならペットの全骨を納めて家で供養できます。 ペットは家族の一員なので、全骨を骨壷に納めて手元に置いておきたいと考える方もいるでしょう。手元供養向けの骨壷の中には、おしゃれなものも多いので、愛するペットの遺骨を入れて毎日家で供養する方も少なくありません。 一般的な骨壷のサイズ 一般的な骨壷のサイズは、小さい骨壷は2寸、大きいものなら尺寸までサイズがさまざまあります。骨壷に使われる「寸」という単位は、骨壺のサイズを表しており、一寸は3.03cmです。一番大きな骨壷の尺寸は、直径が31.5cmになります。 納骨に使われる骨壷は、5寸〜7寸のものが多く、関東と関西で用いられる骨壷のサイズは、関東は7寸、関西では6寸と若干異なります。これは、関東では火葬の後、すべての遺骨を納めるのに対し、関西では喉仏など一部の遺骨しか拾骨しないためです。 また、近年注目を浴びている手元供養に用いられる骨壷は2寸と小さいサイズが主流です。骨壷のサイズは全部で9種類あり、それぞれの大きさは次の通りです。 骨壷の大きさ 縦横のサイズ 2寸 直径約6.5㎝×高さ約7.5㎝ 2.3寸 直径約7.0㎝×高さ約8.5㎝ 3寸 直径約9.5㎝×高さ約11.0㎝ 4寸 直径約12.5㎝×高さ約14.0㎝ 5寸 直径約15.5㎝×高さ約17.5㎝ 6寸 直径約18.0㎝×高さ約20.5㎝ 7寸 直径約22.0㎝×高さ約25.5㎝ 8寸...

「遺骨をお守りとして持ち歩いても大丈夫?」そんな疑問にお答えします
最愛の家族やペットを亡くしたとき、その遺骨をお守りにしたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 ここでは「遺骨をお守りとして持ち歩いても大丈夫?」そんな疑問にお答えしながら、遺骨を手元に置いて供養をしたり、持ち歩いたりする方法についてご紹介します。 遺骨をお守りとして持ち歩くことは可能? 結論からいえば、遺骨をお守りとして持ち歩くことは可能です。日本には、葬儀やお墓に関する決まりごとを定めた「墓地、埋葬等に関する法律」、通称:墓埋法という法律があります。 墓埋法では、遺骨を埋葬する際は、墓地以外で行ってはいけないと定められています。 埋葬は墓地に限られているものの、埋葬しない場合の細かな法律は定められておらず、埋葬するかしないかは基本的には本人の自由です。 法律上問題がないことに加え、個人の価値観が多様化する昨今においては、離れがたい大切な方の遺骨を身近に置いて供養する方も、とても増えています。 なかでも遺骨をお守りとして持ち歩きたい場合は、遺骨の一部を分骨する形となります。 分骨する際の注意点 分骨をする際には「分骨証明書」が必要となる場合があります。お守りとしてペンダントに入れるほどのごく少量であれば必要ありませんが、ある程度の量を分骨する際や、分骨後に納骨、もしくは海洋散骨などをする場合には「分骨証明書」が必要となります。 分骨した遺骨を手元供養する場合は証明書の発行は不要なのですが、将来的に納骨をする可能性も考慮して、念のために発行しておくと安心です。 分骨証明書は火葬場にて発行されますので、火葬の際に分骨する旨を伝えておきましょう。 申請の仕方は火葬場によっても異なるため、火葬場の指示のもと手続きを行ってください。 遺骨をお守りとして持ち歩く方法 遺骨をお守りにする手段としては、遺骨ペンダントで身につけたり、ミニ骨壷に入れて持ち歩く方法があります。それぞれを詳しくご紹介します。 遺骨ペンダント 遺骨ペンダントは、ペンダントトップの中が空洞になっていて、少量の遺骨や遺灰が納められる仕組みになっています。 最近では、遺骨を樹脂で固めるなどの、加工を施した遺骨ペンダントも人気があります。 >未来創想本店|遺骨ペンダントの商品一覧はこちら ミニ骨壷 少量の遺骨が納められるミニ骨壷は、手元供養ではおなじみのアイテムです。 バッグに入れて持ち歩けるサイズのものや、なかには、ポケットサイズのとても小さな骨壷まであります。 インテリア性の高いものが多く、部屋に置いていてもまったく違和感がないのも魅力。ミニ仏壇やミニ仏具とともに、お部屋に祈りのスペースを作るのもおすすめです。 >未来創想本店|ミニ骨壺の商品一覧はこちら >未来創想本店|ミニ仏壇の商品一覧はこちら 遺骨ペンダントやミニ骨壷などの手元供養品はどこで買えるの? 手元供養のアイテムを取り扱う専門店でお求めいただけます。 専門店は手元供養に関する知識が豊富ですので、遺骨の取り扱いについてなど、さまざまなことを相談に乗ってもらいながらアイテムの選択ができるのが大きなメリット。 湿気に弱い遺骨を納めるアイテムには、しっかりとした気密性とそれに合った材質が求められます。 その点、専門店の商品は良質で機能性に優れ、デザイン性が高いものが多いのも魅力です。...
「遺骨をお守りとして持ち歩いても大丈夫?」そんな疑問にお答えします
最愛の家族やペットを亡くしたとき、その遺骨をお守りにしたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 ここでは「遺骨をお守りとして持ち歩いても大丈夫?」そんな疑問にお答えしながら、遺骨を手元に置いて供養をしたり、持ち歩いたりする方法についてご紹介します。 遺骨をお守りとして持ち歩くことは可能? 結論からいえば、遺骨をお守りとして持ち歩くことは可能です。日本には、葬儀やお墓に関する決まりごとを定めた「墓地、埋葬等に関する法律」、通称:墓埋法という法律があります。 墓埋法では、遺骨を埋葬する際は、墓地以外で行ってはいけないと定められています。 埋葬は墓地に限られているものの、埋葬しない場合の細かな法律は定められておらず、埋葬するかしないかは基本的には本人の自由です。 法律上問題がないことに加え、個人の価値観が多様化する昨今においては、離れがたい大切な方の遺骨を身近に置いて供養する方も、とても増えています。 なかでも遺骨をお守りとして持ち歩きたい場合は、遺骨の一部を分骨する形となります。 分骨する際の注意点 分骨をする際には「分骨証明書」が必要となる場合があります。お守りとしてペンダントに入れるほどのごく少量であれば必要ありませんが、ある程度の量を分骨する際や、分骨後に納骨、もしくは海洋散骨などをする場合には「分骨証明書」が必要となります。 分骨した遺骨を手元供養する場合は証明書の発行は不要なのですが、将来的に納骨をする可能性も考慮して、念のために発行しておくと安心です。 分骨証明書は火葬場にて発行されますので、火葬の際に分骨する旨を伝えておきましょう。 申請の仕方は火葬場によっても異なるため、火葬場の指示のもと手続きを行ってください。 遺骨をお守りとして持ち歩く方法 遺骨をお守りにする手段としては、遺骨ペンダントで身につけたり、ミニ骨壷に入れて持ち歩く方法があります。それぞれを詳しくご紹介します。 遺骨ペンダント 遺骨ペンダントは、ペンダントトップの中が空洞になっていて、少量の遺骨や遺灰が納められる仕組みになっています。 最近では、遺骨を樹脂で固めるなどの、加工を施した遺骨ペンダントも人気があります。 >未来創想本店|遺骨ペンダントの商品一覧はこちら ミニ骨壷 少量の遺骨が納められるミニ骨壷は、手元供養ではおなじみのアイテムです。 バッグに入れて持ち歩けるサイズのものや、なかには、ポケットサイズのとても小さな骨壷まであります。 インテリア性の高いものが多く、部屋に置いていてもまったく違和感がないのも魅力。ミニ仏壇やミニ仏具とともに、お部屋に祈りのスペースを作るのもおすすめです。 >未来創想本店|ミニ骨壺の商品一覧はこちら >未来創想本店|ミニ仏壇の商品一覧はこちら 遺骨ペンダントやミニ骨壷などの手元供養品はどこで買えるの? 手元供養のアイテムを取り扱う専門店でお求めいただけます。 専門店は手元供養に関する知識が豊富ですので、遺骨の取り扱いについてなど、さまざまなことを相談に乗ってもらいながらアイテムの選択ができるのが大きなメリット。 湿気に弱い遺骨を納めるアイテムには、しっかりとした気密性とそれに合った材質が求められます。 その点、専門店の商品は良質で機能性に優れ、デザイン性が高いものが多いのも魅力です。...

分骨証明書をご存じですか?
分骨には手続きが必要です。それが分骨証明書。もしかするとずっと先に必要になってくるかもしれません。あまり知られていない分骨証明書についてまとめました。 分骨証明書とは? 分骨するときに発行されるのが分骨証明書。分骨証明書には一般的に故人の名前や性別、死亡年月日などが記されています。火葬場の分骨で発行されるのが“火葬証明書(分骨用)”で、すでに納骨されている場合には“分骨証明書”になります。 分骨証明書は分骨に必要なものではなく、「分骨をどこかに納骨する」というときに必要な書類。なくてもよいのは、分骨したものを散骨するときだけです。 気をつけたいのは手元供養のとき。手元にある間はいらないのですが、なにかあって遺骨をどこかへ納めなければならないときに必要となりますから、念のために収得し、大切に保管してください。 分骨証明書にはいくらかかる? 分骨証明書にはあまりお金はかかりませんが、取るタイミングでほかの諸費用が発生します。 火葬場で発行 火葬場での「火葬証明書(分骨用)」は、自治体にもよりますが1通数百円程度。分骨を希望する人数分を発行してもらいます。火葬費用などが同時に発生しますから、葬儀社に相談しておくのもよいでしょう。 納骨後の発行 納骨後の「分骨証明書」は、お寺や管理事務所などのお墓を管理しているところに発行をお願いします。発行にかかるのはやはり1通数百円程度です。 ただし、骨壷を取り出すのに墓石を動かす必要があるときは、石材店に頼みます。地域にもよりますが、だいたい2〜3万円といわれます。 骨壷を取り出す前には閉眼供養が、分骨したあと、骨壷を元に戻した後には開眼供養が必要なことも。そのときはお布施が必要で相場は1〜3万円とされています。 閉眼供養は”おしょうね抜き”、開眼供養は”おしょうね入れ”などと地方でいろいろな呼び方があります。お布施の金額などは、周囲の人に相談するとよいでしょう。 なくしてしまったときはどうすればいい? 分骨した遺骨をお墓などに納めるために必要な分骨証明書。それは、しばらく手元に置いておいた後、納骨するという形になっても同じです。 では、長年手元で供養しているうちに分骨証明書を紛失してしまったときなどは納骨できないのでしょうか。じつは、分骨証明書は再発行をしてもらえます。分骨した場合は、分骨したお墓の管理者は各自治体に届け出ることになっています。 そのため、分骨前のお墓のある自治体で手続きを行いましょう。故人の氏名、お亡くなりになった日、火葬日がわかれば、何年経っていても比較的スムーズに再発行してもらえます。 お亡くなりになった日や火葬日がわからないと手間取ることがあるかもしれません。特に、ご命日がはっきりわからない場合は再発行が困難になる場合がありますので、それぞれをまとめてどこかに控えておきましょう。 命日などの覚え書きを骨壷にまとめられる? 遺された悲しみを癒すために、分骨を希望する方が増えています。分骨証明書がわからなくなったときに備えて、再発行に必要なメモを骨壷のすぐ近くに残しておくという方法があります。さまざまな骨壷で、いろいろな方法をご紹介しましょう。 命日を刻印できる美しい染付骨壷「蕾(つぼみ)・花」 骨壷そのものにお名前とご命日があれば、特に覚え書きは必要ありません。陶器製の“蕾”シリーズのミニ骨壷は、ほとんどにお名前と月日が刻印できます。 なかでも、陶画工和田一人氏によって、ひとつひとつ優しい花が描かれた“花”シリーズは、2つとして同じものがなく、さらに名入れをすることで、世界でたった一つの骨壷となります。 手のひらで包める愛らしい蕾の形に、優しい志乃釉をかけ、金彩も使用されたあたたかな画風。 見るたびに微笑んでしまいそうな、遺された人の気持ちを明るくするミニ骨壷です。 >豊泉窯のミニ骨つぼ「蕾(つぼみ)・花(はな)」の商品詳細はこちら 片手に包み込めるプチ骨壷「たまごころ」 片手にすっぽりと収まってしまう、小さな卵形のミニミニ骨壷“たまごころ”。 たまごころは、遺骨を湿気からしっかり守るため、中蓋と外蓋のある二重構造になっています。そのため、中蓋の上にも小さな空間が。小さなメモなら畳んで収められますので、ご命日とお名前・火葬日のメモを入れておかれると安心です。...
分骨証明書をご存じですか?
分骨には手続きが必要です。それが分骨証明書。もしかするとずっと先に必要になってくるかもしれません。あまり知られていない分骨証明書についてまとめました。 分骨証明書とは? 分骨するときに発行されるのが分骨証明書。分骨証明書には一般的に故人の名前や性別、死亡年月日などが記されています。火葬場の分骨で発行されるのが“火葬証明書(分骨用)”で、すでに納骨されている場合には“分骨証明書”になります。 分骨証明書は分骨に必要なものではなく、「分骨をどこかに納骨する」というときに必要な書類。なくてもよいのは、分骨したものを散骨するときだけです。 気をつけたいのは手元供養のとき。手元にある間はいらないのですが、なにかあって遺骨をどこかへ納めなければならないときに必要となりますから、念のために収得し、大切に保管してください。 分骨証明書にはいくらかかる? 分骨証明書にはあまりお金はかかりませんが、取るタイミングでほかの諸費用が発生します。 火葬場で発行 火葬場での「火葬証明書(分骨用)」は、自治体にもよりますが1通数百円程度。分骨を希望する人数分を発行してもらいます。火葬費用などが同時に発生しますから、葬儀社に相談しておくのもよいでしょう。 納骨後の発行 納骨後の「分骨証明書」は、お寺や管理事務所などのお墓を管理しているところに発行をお願いします。発行にかかるのはやはり1通数百円程度です。 ただし、骨壷を取り出すのに墓石を動かす必要があるときは、石材店に頼みます。地域にもよりますが、だいたい2〜3万円といわれます。 骨壷を取り出す前には閉眼供養が、分骨したあと、骨壷を元に戻した後には開眼供養が必要なことも。そのときはお布施が必要で相場は1〜3万円とされています。 閉眼供養は”おしょうね抜き”、開眼供養は”おしょうね入れ”などと地方でいろいろな呼び方があります。お布施の金額などは、周囲の人に相談するとよいでしょう。 なくしてしまったときはどうすればいい? 分骨した遺骨をお墓などに納めるために必要な分骨証明書。それは、しばらく手元に置いておいた後、納骨するという形になっても同じです。 では、長年手元で供養しているうちに分骨証明書を紛失してしまったときなどは納骨できないのでしょうか。じつは、分骨証明書は再発行をしてもらえます。分骨した場合は、分骨したお墓の管理者は各自治体に届け出ることになっています。 そのため、分骨前のお墓のある自治体で手続きを行いましょう。故人の氏名、お亡くなりになった日、火葬日がわかれば、何年経っていても比較的スムーズに再発行してもらえます。 お亡くなりになった日や火葬日がわからないと手間取ることがあるかもしれません。特に、ご命日がはっきりわからない場合は再発行が困難になる場合がありますので、それぞれをまとめてどこかに控えておきましょう。 命日などの覚え書きを骨壷にまとめられる? 遺された悲しみを癒すために、分骨を希望する方が増えています。分骨証明書がわからなくなったときに備えて、再発行に必要なメモを骨壷のすぐ近くに残しておくという方法があります。さまざまな骨壷で、いろいろな方法をご紹介しましょう。 命日を刻印できる美しい染付骨壷「蕾(つぼみ)・花」 骨壷そのものにお名前とご命日があれば、特に覚え書きは必要ありません。陶器製の“蕾”シリーズのミニ骨壷は、ほとんどにお名前と月日が刻印できます。 なかでも、陶画工和田一人氏によって、ひとつひとつ優しい花が描かれた“花”シリーズは、2つとして同じものがなく、さらに名入れをすることで、世界でたった一つの骨壷となります。 手のひらで包める愛らしい蕾の形に、優しい志乃釉をかけ、金彩も使用されたあたたかな画風。 見るたびに微笑んでしまいそうな、遺された人の気持ちを明るくするミニ骨壷です。 >豊泉窯のミニ骨つぼ「蕾(つぼみ)・花(はな)」の商品詳細はこちら 片手に包み込めるプチ骨壷「たまごころ」 片手にすっぽりと収まってしまう、小さな卵形のミニミニ骨壷“たまごころ”。 たまごころは、遺骨を湿気からしっかり守るため、中蓋と外蓋のある二重構造になっています。そのため、中蓋の上にも小さな空間が。小さなメモなら畳んで収められますので、ご命日とお名前・火葬日のメモを入れておかれると安心です。...

おすすめのペット用分骨アクセサリー3選
家族同様のペット。虹の橋を渡ったペットを偲ぶため、分骨用のアクセサリーを作りました。思い出してあげるのは、何よりの供養。身近に遺骨をおいて、在りし日の姿を偲んであげましょう。 分骨してもいい?ペットの供養事情 人間の場合でも”分骨すると浮かばれない”というお考えもありますが、決してそうではありません。魂を入れる器としての役割を終えた体の名残、この世に生きた証がご遺骨です。 ペットも同じ。寂しがり屋だったり、甘えん坊だった大切なペットといつも一緒にいてあげたいという想いで、分骨して手元に置いたり、アクセサリーに納めるのは悪いことではありません。 ペットも家族と同じように供養 しっかり手をかけ、大切に世話をしたペットが死んでしまったときの喪失感は、家族を亡くしたときと同じように大きく、深い悲しみに包まれます。 ペットは、何よりも飼い主を思っています。悲しみを落ち着け乗り越えられるならば、分骨し手元で供養されるのをペット自身が望むかもしれません。 ペットのための手元供養〜足あと・シルバー ペットを飼った人なら、プクプクした肉球を触ったことは必ずあるでしょう。リラックスしているときに見せるかわいい肉球を、モチーフにしたペット用の分骨ペンダントです。 鳴き声も心に残りますが、走り回る足音、じゃれてきたときや遊ぶときに見せた仕草も忘れがたいものです。 年代を問わず使用できる肉球型シルバー 古来から魔除けとしても使われるシルバーで肉球をかたどり、生きた足跡をイメージしました。手入れとともに深みを増す銀のアクセサリーは、年代を問わず使用することができます。 >ペットのための手元供養「足あと・シルバー」の商品詳細はこちら ペットのための手元供養〜ドッグボーン・ゴールド 骨型のガムや骨型のおもちゃ、骨型のビスケット…。犬のいる家庭には、なにかしら骨型のアイテムがあります。 愛犬がいなくなり、そのようなアイテムが一つ一つなくなる寂しさを埋める骨型の分骨ペンダントは、普段使いができるようかための14金で作られています。 骨型アイテムを身につけ散歩へ ゴールドのやわらかな輝きは、愛犬のつやつやした毛並みを思い出させるかもしれません。お気に入りの骨型のアイテムを見せたときの嬉しそうな様子を偲ぶアクセサリーとして、手近な供養として、分骨を納めて身につけ再び散歩へお出かけください。 >ペットのための手元供養「ドッグボーン・ゴールド」の商品詳細はこちら ペットのための手元供養〜ドッグボーン・シルバー925 >ペットのための手元供養「ドッグボーン・シルバー925」の商品詳細はこちら ペットを分骨アクセサリーで偲びましょう 話ができないペットへかける愛情は、ときに家族以上のものがあるでしょう。そんなペットを亡くしてしまったときの大きな喪失感が”ペットロス”へとつながります。そんな悲しみを少しでも癒すために、分骨して身近におくのも一つの方法です。 未来創想では、分骨用のアクセサリーをはじめ、ペットをなくされた方々を心が癒せる手元供養品をご提案しております。
おすすめのペット用分骨アクセサリー3選
家族同様のペット。虹の橋を渡ったペットを偲ぶため、分骨用のアクセサリーを作りました。思い出してあげるのは、何よりの供養。身近に遺骨をおいて、在りし日の姿を偲んであげましょう。 分骨してもいい?ペットの供養事情 人間の場合でも”分骨すると浮かばれない”というお考えもありますが、決してそうではありません。魂を入れる器としての役割を終えた体の名残、この世に生きた証がご遺骨です。 ペットも同じ。寂しがり屋だったり、甘えん坊だった大切なペットといつも一緒にいてあげたいという想いで、分骨して手元に置いたり、アクセサリーに納めるのは悪いことではありません。 ペットも家族と同じように供養 しっかり手をかけ、大切に世話をしたペットが死んでしまったときの喪失感は、家族を亡くしたときと同じように大きく、深い悲しみに包まれます。 ペットは、何よりも飼い主を思っています。悲しみを落ち着け乗り越えられるならば、分骨し手元で供養されるのをペット自身が望むかもしれません。 ペットのための手元供養〜足あと・シルバー ペットを飼った人なら、プクプクした肉球を触ったことは必ずあるでしょう。リラックスしているときに見せるかわいい肉球を、モチーフにしたペット用の分骨ペンダントです。 鳴き声も心に残りますが、走り回る足音、じゃれてきたときや遊ぶときに見せた仕草も忘れがたいものです。 年代を問わず使用できる肉球型シルバー 古来から魔除けとしても使われるシルバーで肉球をかたどり、生きた足跡をイメージしました。手入れとともに深みを増す銀のアクセサリーは、年代を問わず使用することができます。 >ペットのための手元供養「足あと・シルバー」の商品詳細はこちら ペットのための手元供養〜ドッグボーン・ゴールド 骨型のガムや骨型のおもちゃ、骨型のビスケット…。犬のいる家庭には、なにかしら骨型のアイテムがあります。 愛犬がいなくなり、そのようなアイテムが一つ一つなくなる寂しさを埋める骨型の分骨ペンダントは、普段使いができるようかための14金で作られています。 骨型アイテムを身につけ散歩へ ゴールドのやわらかな輝きは、愛犬のつやつやした毛並みを思い出させるかもしれません。お気に入りの骨型のアイテムを見せたときの嬉しそうな様子を偲ぶアクセサリーとして、手近な供養として、分骨を納めて身につけ再び散歩へお出かけください。 >ペットのための手元供養「ドッグボーン・ゴールド」の商品詳細はこちら ペットのための手元供養〜ドッグボーン・シルバー925 >ペットのための手元供養「ドッグボーン・シルバー925」の商品詳細はこちら ペットを分骨アクセサリーで偲びましょう 話ができないペットへかける愛情は、ときに家族以上のものがあるでしょう。そんなペットを亡くしてしまったときの大きな喪失感が”ペットロス”へとつながります。そんな悲しみを少しでも癒すために、分骨して身近におくのも一つの方法です。 未来創想では、分骨用のアクセサリーをはじめ、ペットをなくされた方々を心が癒せる手元供養品をご提案しております。

亡き人とともに~おすすめのおしゃれ分骨アクセサリー
分骨したご遺骨をアクセサリーに納め、常に身につけることで、深い悲しみの慰めになります。”いつも一緒”という安心感を得られる分骨アクセサリーの様々な形を、ご紹介します。 深い悲しみを癒す分骨アクセサリー 分骨した遺骨や遺髪をお守りとしていつも持ちたいという想いは、昔も変わらないようで、江戸時代には遺髪を漆で固めたかんざしなどがあったようです。 大切な人を亡くした悲しみは、いつの時代も同じ。深い悲しみを乗り越えるためのものを、作り出していったのでしょう。 供養だけでなく自分の気持ちを落ち着かせるために、分骨したお骨を身につけられるアクセサリーを選ぶ方が増えています。 遺骨ジュエリー〜See You Collection 想いを表すハート、見えなくても空にあるスター、魂の象徴とされるバタフライの3種類のデザインと6色のレジンカラーから好みを選び、セミオーダー式の分骨用アクセサリーです。 日常使いできるジュエリー 日常に使いやすい小さなデザインは、ネックレスとリングの2種類があります。わずかな遺骨をモザイクのように美しく並べ、レジンで固めるのは、まさに職人技。 ほかに、男性も身につけやすいやや太めのリングも、2種類のシャープなデザインでご用意いたしました。 >遺骨ジュエリー「See You Collection」の商品一覧はこちら 遺骨ジュエリー〜AZUL Collection アズールコレクションは、わずかなご遺骨をエナメルで固めています。エナメルで固めることで強度と防水力がアップ。 完全防水により、ご遺骨の劣化も防げるようになりました。クリアな色のなかに浮かぶご遺骨は、雲のようにも万華鏡の一部のようにも見えます。 トップとカラーの組み合わせ 8種類のペンダントトップと1種類のリング、5色のカラーから選んで組み合わせるセミオーダーの分骨用アクセサリーです。台座に宝石をあしらうこともでき、世界で一つだけの遺骨アクセサリーにできます。 >遺骨ジュエリー「AZUL Collection」の商品一覧はこちら 遺骨ペンダント シルバー 永遠のメロディー 音楽が大好きだった方を偲ぶアクセサリーとして最適な、尻尾のついた八分音符型のペンダント。 分骨用のペンダントとは思えないキュートなデザインで、やや大振りの音符の頭に分骨し、身につけることができます。 音楽と故人を重ね 磨くことで深みが出るシルバーでつくり、永遠のメロディーと名付けました。見えなくても、そこにあるのが分かる音楽に、故人を重ね偲ぶことができるでしょう。生活防水仕様で仕上げてあります。 >遺骨ペンダント「シルバー 永遠のメロディー」の商品詳細はこちら 遺骨ペンダント シルバー イルカ・Dolphin...
亡き人とともに~おすすめのおしゃれ分骨アクセサリー
分骨したご遺骨をアクセサリーに納め、常に身につけることで、深い悲しみの慰めになります。”いつも一緒”という安心感を得られる分骨アクセサリーの様々な形を、ご紹介します。 深い悲しみを癒す分骨アクセサリー 分骨した遺骨や遺髪をお守りとしていつも持ちたいという想いは、昔も変わらないようで、江戸時代には遺髪を漆で固めたかんざしなどがあったようです。 大切な人を亡くした悲しみは、いつの時代も同じ。深い悲しみを乗り越えるためのものを、作り出していったのでしょう。 供養だけでなく自分の気持ちを落ち着かせるために、分骨したお骨を身につけられるアクセサリーを選ぶ方が増えています。 遺骨ジュエリー〜See You Collection 想いを表すハート、見えなくても空にあるスター、魂の象徴とされるバタフライの3種類のデザインと6色のレジンカラーから好みを選び、セミオーダー式の分骨用アクセサリーです。 日常使いできるジュエリー 日常に使いやすい小さなデザインは、ネックレスとリングの2種類があります。わずかな遺骨をモザイクのように美しく並べ、レジンで固めるのは、まさに職人技。 ほかに、男性も身につけやすいやや太めのリングも、2種類のシャープなデザインでご用意いたしました。 >遺骨ジュエリー「See You Collection」の商品一覧はこちら 遺骨ジュエリー〜AZUL Collection アズールコレクションは、わずかなご遺骨をエナメルで固めています。エナメルで固めることで強度と防水力がアップ。 完全防水により、ご遺骨の劣化も防げるようになりました。クリアな色のなかに浮かぶご遺骨は、雲のようにも万華鏡の一部のようにも見えます。 トップとカラーの組み合わせ 8種類のペンダントトップと1種類のリング、5色のカラーから選んで組み合わせるセミオーダーの分骨用アクセサリーです。台座に宝石をあしらうこともでき、世界で一つだけの遺骨アクセサリーにできます。 >遺骨ジュエリー「AZUL Collection」の商品一覧はこちら 遺骨ペンダント シルバー 永遠のメロディー 音楽が大好きだった方を偲ぶアクセサリーとして最適な、尻尾のついた八分音符型のペンダント。 分骨用のペンダントとは思えないキュートなデザインで、やや大振りの音符の頭に分骨し、身につけることができます。 音楽と故人を重ね 磨くことで深みが出るシルバーでつくり、永遠のメロディーと名付けました。見えなくても、そこにあるのが分かる音楽に、故人を重ね偲ぶことができるでしょう。生活防水仕様で仕上げてあります。 >遺骨ペンダント「シルバー 永遠のメロディー」の商品詳細はこちら 遺骨ペンダント シルバー イルカ・Dolphin...










