お墓に関する記事

墓の種類と選び方|現代の供養スタイルを分かりやすく解説
「お墓=墓地に建てる石碑」というイメージは、いまや選択肢の一つに過ぎません。少子高齢化や居住地の移動、宗教観・価値観の多様化により、永代供養墓・納骨堂・樹木葬・散骨・手元供養など“墓の種類”は大きく広がりました。 本記事では主な供養の選択肢について紹介し、ライフスタイルに合った選び方のポイントを解説します。あわせて、自宅で無理なく続けられる手元供養アイテムもご紹介しますので、ぜひ参考にされてください。 知っておきたい墓の主な種類 まずは墓の種類についてご紹介します。 一般墓(従来型の墓石) 「一般墓(先祖代々の墓)」は、日本で最もよく知られた形式です。墓石を建立し、子孫が承継していくもので、家という単位で先祖を守る文化を反映しています。 メリットとしては、故人や親族のお参りが一か所でできる利便性や、地域社会に受け入れられやすい習慣性が挙げられます。しかし一方で、跡継ぎが必要であることや、管理や維持費が負担になる点がデメリットです 永代供養墓 永代供養墓には「個別安置型」「集合安置型」「合祀型」といった方式があり、寺院などが責任をもって供養・管理するものです 。 たとえば「個別安置型」は期限付きで骨壺を個別に安置し、その後合祀へ移す形式。一方で「合祀型」は他の方と合同で埋葬され、永続供養がされるため、後継ぎのいない人でも安心して選べる選択肢として支持されています。 納骨堂(屋内型) 納骨堂とは、室内やビル内などに骨壺を安置するスタイルで、近年ますます多様化しています。中でも「自動搬送式納骨堂」は、参拝時に自動で骨壺が搬送されるためプライバシー保護にも優れており、都市部で注目されています。 さらに仏壇式納骨壇やロッカー形式など、小スペースで費用も抑えられ、承継者や利便性を重視する現代ライフスタイルにマッチした形です。 樹木葬・海洋散骨 自然環境にやさしく、精神的にも美しい供養スタイルとして「樹木葬」が人気です。墓標の代わりに樹木を墓標とし、永代供養がセットされるケースも多く見られます。 また、「海洋散骨」は文字通り海に散骨するもので、自然への回帰を願う方や、墓地を持ちたくない方に適した供養方法です。 手元供養 近年、手元供養(骨壺を自宅で管理)や「ペットと眠る墓」「ペット共葬墓」など、多様な供養スタイルも選べる時代になりました。 特にペット共葬は、家族同然のペットを永遠のつながりとして尊重したいという現代の価値観にマッチしており、新たな供養ニーズに応える形です。 地域特有の墓もある 日本各地には地域特有の墓文化もあります。たとえば沖縄では「屋形墓(家形墓)」と呼ばれる、家屋を模した墓が伝統的に存在し、琉球独自の風習を今に伝えています。 また、中世鎌倉の「やぐら(yagura)」という人工の洞窟墓や、古墳時代の「前方後円墳」なども、墓の歴史と文化的背景を示す重要な事例です。 >ミニ仏壇の商品はこちら 墓の選び方・判断ポイント6つ 後継者の有無:将来の維持を誰が担うのか。継承負担が難しければ永代供養墓や納骨堂、自宅供養が現実的です。 立地・アクセス:お参り頻度や移動手段に合わせて無理のない距離を選びましょう。 初期費用と維持費:建立費・永代使用料・管理費・更新料など、総額で比較します。 宗教・習俗:寺院の檀家要件や宗派の作法、改葬のしやすさも確認しましょう。 場所へのこだわり:物理的な墓の場所を重視するか、自然や自宅での祀り方を重視するかで決める。...
墓の種類と選び方|現代の供養スタイルを分かりやすく解説
「お墓=墓地に建てる石碑」というイメージは、いまや選択肢の一つに過ぎません。少子高齢化や居住地の移動、宗教観・価値観の多様化により、永代供養墓・納骨堂・樹木葬・散骨・手元供養など“墓の種類”は大きく広がりました。 本記事では主な供養の選択肢について紹介し、ライフスタイルに合った選び方のポイントを解説します。あわせて、自宅で無理なく続けられる手元供養アイテムもご紹介しますので、ぜひ参考にされてください。 知っておきたい墓の主な種類 まずは墓の種類についてご紹介します。 一般墓(従来型の墓石) 「一般墓(先祖代々の墓)」は、日本で最もよく知られた形式です。墓石を建立し、子孫が承継していくもので、家という単位で先祖を守る文化を反映しています。 メリットとしては、故人や親族のお参りが一か所でできる利便性や、地域社会に受け入れられやすい習慣性が挙げられます。しかし一方で、跡継ぎが必要であることや、管理や維持費が負担になる点がデメリットです 永代供養墓 永代供養墓には「個別安置型」「集合安置型」「合祀型」といった方式があり、寺院などが責任をもって供養・管理するものです 。 たとえば「個別安置型」は期限付きで骨壺を個別に安置し、その後合祀へ移す形式。一方で「合祀型」は他の方と合同で埋葬され、永続供養がされるため、後継ぎのいない人でも安心して選べる選択肢として支持されています。 納骨堂(屋内型) 納骨堂とは、室内やビル内などに骨壺を安置するスタイルで、近年ますます多様化しています。中でも「自動搬送式納骨堂」は、参拝時に自動で骨壺が搬送されるためプライバシー保護にも優れており、都市部で注目されています。 さらに仏壇式納骨壇やロッカー形式など、小スペースで費用も抑えられ、承継者や利便性を重視する現代ライフスタイルにマッチした形です。 樹木葬・海洋散骨 自然環境にやさしく、精神的にも美しい供養スタイルとして「樹木葬」が人気です。墓標の代わりに樹木を墓標とし、永代供養がセットされるケースも多く見られます。 また、「海洋散骨」は文字通り海に散骨するもので、自然への回帰を願う方や、墓地を持ちたくない方に適した供養方法です。 手元供養 近年、手元供養(骨壺を自宅で管理)や「ペットと眠る墓」「ペット共葬墓」など、多様な供養スタイルも選べる時代になりました。 特にペット共葬は、家族同然のペットを永遠のつながりとして尊重したいという現代の価値観にマッチしており、新たな供養ニーズに応える形です。 地域特有の墓もある 日本各地には地域特有の墓文化もあります。たとえば沖縄では「屋形墓(家形墓)」と呼ばれる、家屋を模した墓が伝統的に存在し、琉球独自の風習を今に伝えています。 また、中世鎌倉の「やぐら(yagura)」という人工の洞窟墓や、古墳時代の「前方後円墳」なども、墓の歴史と文化的背景を示す重要な事例です。 >ミニ仏壇の商品はこちら 墓の選び方・判断ポイント6つ 後継者の有無:将来の維持を誰が担うのか。継承負担が難しければ永代供養墓や納骨堂、自宅供養が現実的です。 立地・アクセス:お参り頻度や移動手段に合わせて無理のない距離を選びましょう。 初期費用と維持費:建立費・永代使用料・管理費・更新料など、総額で比較します。 宗教・習俗:寺院の檀家要件や宗派の作法、改葬のしやすさも確認しましょう。 場所へのこだわり:物理的な墓の場所を重視するか、自然や自宅での祀り方を重視するかで決める。...

遺骨を分骨するのは良くないの?分骨が選ばれる理由や目的、分骨するやり方を解説
手元供養のご相談の中でもっとも多いのが「分骨は良くないと聞いたのですが…?」という心配事。 分骨はデリケートな問題ですので、正しい知識を持っていないと、他の親族にもなかなか理解が得られないものです。 そこで今回は「分骨は良くないの?」そんな疑問の解決を含め、分骨についての知識や方法をまとめました。 分骨とは? 分骨とは、文字通りご遺骨の一部を取り分けることです。目的はさまざまですが、主に 遠方に離れて住む遺族がそれぞれに故人を供養するため 宗教上の習わしとして 離れがたい故人の身代わりとして手元供養をするため などがあります。 お墓に入れる分骨とは? お墓に入れる分骨とは、家族がそれぞれ所有するお墓に個人の遺骨を埋葬する方法です。遠方に家族の所有するお墓がある場合、それぞれのお墓で故人を弔いたいといった気持ちから分骨される方がいます。 人によっては分骨した遺骨の一部を納骨堂に納める方もおり、分骨は様々なニーズから選択されています。 お骨を分けてはいけない?分骨は良くないといわれる理由 分骨には然るべき目的があるにもかかわらず「良くない」といわれることが多々あります。そういった意見が聞かれる理由には、ある種の思い込みがあるようです。 分骨は違法だと思っている 分骨すると故人が成仏できない 宗教上縁起が悪い 分骨すると来世で五体満足にならない ここからは、これらの誤解について詳しく解説していきます。 分骨は違法なの? 分骨を行う上で気になるのが、分骨が違法ではないのか?ということです。 結論から述べると、分骨は違法ではありません。きちんと手順を踏んでおけば、法律上まったく問題はないのです。 分骨は違法ではないと法律に明記されている 法律でも「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条にて、下記のように明記されています。 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。 引用元:墓地、埋葬等に関する法律施行規則 つまり、きちんと墓地の管理者に書類を提出して手順を踏めば、分骨はなんら問題はないということ。「分骨は良くない」というイメージから「分骨は違法」と誤解しているケースも多いようです。 分骨は古来から行われてきた習慣 なかには「分骨は良くないと昔から言われている」という意見もありますが、実は分骨そのものは古くから行われてきた習慣です。 尊い習慣とされる分骨...
遺骨を分骨するのは良くないの?分骨が選ばれる理由や目的、分骨するやり方を解説
手元供養のご相談の中でもっとも多いのが「分骨は良くないと聞いたのですが…?」という心配事。 分骨はデリケートな問題ですので、正しい知識を持っていないと、他の親族にもなかなか理解が得られないものです。 そこで今回は「分骨は良くないの?」そんな疑問の解決を含め、分骨についての知識や方法をまとめました。 分骨とは? 分骨とは、文字通りご遺骨の一部を取り分けることです。目的はさまざまですが、主に 遠方に離れて住む遺族がそれぞれに故人を供養するため 宗教上の習わしとして 離れがたい故人の身代わりとして手元供養をするため などがあります。 お墓に入れる分骨とは? お墓に入れる分骨とは、家族がそれぞれ所有するお墓に個人の遺骨を埋葬する方法です。遠方に家族の所有するお墓がある場合、それぞれのお墓で故人を弔いたいといった気持ちから分骨される方がいます。 人によっては分骨した遺骨の一部を納骨堂に納める方もおり、分骨は様々なニーズから選択されています。 お骨を分けてはいけない?分骨は良くないといわれる理由 分骨には然るべき目的があるにもかかわらず「良くない」といわれることが多々あります。そういった意見が聞かれる理由には、ある種の思い込みがあるようです。 分骨は違法だと思っている 分骨すると故人が成仏できない 宗教上縁起が悪い 分骨すると来世で五体満足にならない ここからは、これらの誤解について詳しく解説していきます。 分骨は違法なの? 分骨を行う上で気になるのが、分骨が違法ではないのか?ということです。 結論から述べると、分骨は違法ではありません。きちんと手順を踏んでおけば、法律上まったく問題はないのです。 分骨は違法ではないと法律に明記されている 法律でも「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条にて、下記のように明記されています。 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。 引用元:墓地、埋葬等に関する法律施行規則 つまり、きちんと墓地の管理者に書類を提出して手順を踏めば、分骨はなんら問題はないということ。「分骨は良くない」というイメージから「分骨は違法」と誤解しているケースも多いようです。 分骨は古来から行われてきた習慣 なかには「分骨は良くないと昔から言われている」という意見もありますが、実は分骨そのものは古くから行われてきた習慣です。 尊い習慣とされる分骨...

お墓が遺骨でいっぱい!どうすればいい?
お墓に遺骨がいっぱいで、新たに骨壷を納めるスペースがない…。先祖代々お墓を受け継いでいるご家庭などから、こんなお悩みがときおり訊かれます。どうすればよいか、対処法についてまとめてみました。 お墓に遺骨が増えてしまったときの対処法 「お墓が遺骨でいっぱいになったら、新しいお墓を建てなくてはならないのでしょうか?」そうお悩みになる方がいらっしゃいますが、必ずしもその必要はありません。 新しくお墓を建てると莫大な費用がかかりますし、複数のお墓を管理することになるので、負担はさらに増えるばかりです。 ここからは、もっと現実的に問題を解決できる、2つの対処法をご紹介します。 遺骨を土に還す 地域やお墓のタイプによっては、カロート(お墓の中で骨壷を納める部分)の底が直接地面の土になっています。 一般的にこうしたお墓で行われるのは、古い遺骨を骨壷から出し、カロートの土の上に直接広げてあげること。土に埋める場合もあります。 カロートの底がコンクリートでも、中央に小さく土のスペースが開けてあるお墓も。そのようなお墓では、遺骨を小さくして土のスペースへ入れます。 遺骨はお墓の中にありますが、骨壷が無くなる分スペースが空き、広げた遺骨はいずれ分解されて土へと還っていきます。このような形をとれば、何代にもわたってお墓を使用していただくことが可能です。 遺骨を粉骨する カロートの底部がすべてコンクリートのお墓の場合は、遺骨を土には還せません。しかし、遺骨を細かく砕いてかさを減らすという方法があります。 それが“粉骨”です。 遺骨を砕くのに抵抗を感じるかもしれませんが、粉骨は手元供養や散骨などの際にも行われている方法。 そもそも、お骨拾いの場でも骨壷に入りやすいよう遺骨を砕きますから、宗教的にも法律的にも何も問題はありません。また、古い遺骨は自然に崩れる場合もあります。 粉骨した後、複数の遺骨を1つの骨壷にまとめれば、新たな遺骨を納めるスペースを確保できます。 古い遺骨を対処するタイミング お墓がいっぱいになってきたら、古い遺骨から土に還すなどの対処を行います。弔い上げといわれる三十三回忌を終えた遺骨や、亡くなって50年を過ぎた遺骨を対象にするとよいでしょう。 要らなくなった骨壷は? いずれの方法をとっても、いくつかの古い骨壷が不要になります。空の骨壷は、単なる“容れもの”ですので、自治体の決まりに従って処分してもかまいません。 どうしても心情的に難しいという場合には、一部の葬儀社などで請け負ってくれることもありますので、依頼するとよいでしょう。 個性豊かなミニ骨壷で温もりを 遺骨を土地に還すとき、または粉骨してまとめるときに、お一人分ずつの遺骨を一部とりわけて、それぞれ小さな骨壷に移し替えるのもおすすめです。 現在の“ミニ骨壷”は、素材や大きさもさまざまで、多彩なデザインのものが登場しています。 エレガントで美しいタイプ、やさしく愛らしいタイプ、スタイリッシュなタイプなど、故人お一人お一人のイメージや個性に合わせて選べば、より故人の面影を感じていただけるでしょう。 お墓の中のご先祖様や亡くなった方々にも、ご家族の温もりをお伝えいただけるかと思います。 >ミニ骨壷 の商品一覧はこちら お墓にも納められる個性あふれたミニ骨壷10選 お墓の中でもお仏壇でもスペースをとらない、小さな骨壷。小さいとはいえ、遺骨の大敵の湿気を寄せ付けない工夫がされた骨壷ばかりです。...
お墓が遺骨でいっぱい!どうすればいい?
お墓に遺骨がいっぱいで、新たに骨壷を納めるスペースがない…。先祖代々お墓を受け継いでいるご家庭などから、こんなお悩みがときおり訊かれます。どうすればよいか、対処法についてまとめてみました。 お墓に遺骨が増えてしまったときの対処法 「お墓が遺骨でいっぱいになったら、新しいお墓を建てなくてはならないのでしょうか?」そうお悩みになる方がいらっしゃいますが、必ずしもその必要はありません。 新しくお墓を建てると莫大な費用がかかりますし、複数のお墓を管理することになるので、負担はさらに増えるばかりです。 ここからは、もっと現実的に問題を解決できる、2つの対処法をご紹介します。 遺骨を土に還す 地域やお墓のタイプによっては、カロート(お墓の中で骨壷を納める部分)の底が直接地面の土になっています。 一般的にこうしたお墓で行われるのは、古い遺骨を骨壷から出し、カロートの土の上に直接広げてあげること。土に埋める場合もあります。 カロートの底がコンクリートでも、中央に小さく土のスペースが開けてあるお墓も。そのようなお墓では、遺骨を小さくして土のスペースへ入れます。 遺骨はお墓の中にありますが、骨壷が無くなる分スペースが空き、広げた遺骨はいずれ分解されて土へと還っていきます。このような形をとれば、何代にもわたってお墓を使用していただくことが可能です。 遺骨を粉骨する カロートの底部がすべてコンクリートのお墓の場合は、遺骨を土には還せません。しかし、遺骨を細かく砕いてかさを減らすという方法があります。 それが“粉骨”です。 遺骨を砕くのに抵抗を感じるかもしれませんが、粉骨は手元供養や散骨などの際にも行われている方法。 そもそも、お骨拾いの場でも骨壷に入りやすいよう遺骨を砕きますから、宗教的にも法律的にも何も問題はありません。また、古い遺骨は自然に崩れる場合もあります。 粉骨した後、複数の遺骨を1つの骨壷にまとめれば、新たな遺骨を納めるスペースを確保できます。 古い遺骨を対処するタイミング お墓がいっぱいになってきたら、古い遺骨から土に還すなどの対処を行います。弔い上げといわれる三十三回忌を終えた遺骨や、亡くなって50年を過ぎた遺骨を対象にするとよいでしょう。 要らなくなった骨壷は? いずれの方法をとっても、いくつかの古い骨壷が不要になります。空の骨壷は、単なる“容れもの”ですので、自治体の決まりに従って処分してもかまいません。 どうしても心情的に難しいという場合には、一部の葬儀社などで請け負ってくれることもありますので、依頼するとよいでしょう。 個性豊かなミニ骨壷で温もりを 遺骨を土地に還すとき、または粉骨してまとめるときに、お一人分ずつの遺骨を一部とりわけて、それぞれ小さな骨壷に移し替えるのもおすすめです。 現在の“ミニ骨壷”は、素材や大きさもさまざまで、多彩なデザインのものが登場しています。 エレガントで美しいタイプ、やさしく愛らしいタイプ、スタイリッシュなタイプなど、故人お一人お一人のイメージや個性に合わせて選べば、より故人の面影を感じていただけるでしょう。 お墓の中のご先祖様や亡くなった方々にも、ご家族の温もりをお伝えいただけるかと思います。 >ミニ骨壷 の商品一覧はこちら お墓にも納められる個性あふれたミニ骨壷10選 お墓の中でもお仏壇でもスペースをとらない、小さな骨壷。小さいとはいえ、遺骨の大敵の湿気を寄せ付けない工夫がされた骨壷ばかりです。...

夫婦と遺族の想いに寄り添う「夫婦墓」とは?
夫婦が2人で入るためのお墓を「夫婦墓」と言います。夫婦墓は生涯を寄り添った2人の想いを形にできるだけでなく、継承を前提としないため、自分たちが旅立ったあとの「管理の不安」を解消してくれます。少子化やライフスタイルの多様化から、さまざまな形態を選べるようになったお墓。今回は、その中から夫婦墓についてご紹介します。 夫婦墓とは? 近年、注目を集めるようになったお墓のひとつが「夫婦墓(ふうふばか・めおとばか)」です。 夫婦墓とは、夫婦として過ごした2人だけが入るお墓のこと。 生前に夫婦として過ごした2人が、仏になってからも一緒にいることは縁起が良く、夫婦墓を作った家は、子々孫々にわたって幸せな家庭を築けるとも伝えられています。 継承を前提としない形が喜ばれている 夫婦墓が広く喜ばれている理由として、継承を前提としないお墓である点が挙げられます。 夫婦が2人だけで入る夫婦墓は、先祖代々受け継がれるお墓と違い、一代限りの供養が基本です。 そのため、お墓の管理や法要を寺院や自治体が請け負う「永代供養」が基本となることから、自分たちが亡くなった後のお墓の管理を心配する必要がありません。 子どもがいない方や、子どもが遠方に住んでいる方、家族や親戚への負担を心配される方にとって、夫婦墓は安心して眠ることができるお墓のスタイルと呼ぶことができるでしょう。 夫婦墓のメリットとデメリット それでは、夫婦墓についてより詳しく知るために、夫婦墓のメリットとデメリットについて見ていきましょう。 夫婦墓のメリット 夫婦墓のメリットとして、「夫婦の希望にあうお墓を選べる」点が挙げられます。 お墓に対する考え方が多様化するにつれて、自分たちの希望に添ったお墓選びも広まってきました。 デザインや場所を夫婦の希望にあわせて建てることができる点は、夫婦墓のメリットのひとつと言えるでしょう。 また、夫婦一代限りのお墓なので、寺院の場所にもこだわる必要がありません。 先祖の宗派を気にすることなく、信仰している宗教にあったお墓を選べる点も大きなメリットでしょう。 夫婦墓のデメリット 夫婦墓のデメリットには、「安置期間」に関わるものが挙げられます。 永代供養をする場合、一般的には三十三回忌や五十回忌など寺院によって安置する期間が決められています。 この期間は個別に遺骨を安置してもらえますが、期間を過ぎると合葬されることになります。 他の人たちと一緒に埋葬される合葬の形態を好まない方にはデメリットと言えるでしょう。 また、一度合葬されてしまうと、個別に遺骨を取り出すことができません。例えば、ご家族が個別の供養を望まれている場合などは注意が必要です。 夫婦墓の費用はどれくらい? お墓を建てるとなると、費用がどれくらいかかるのかは気になる項目です。 夫婦墓では、どれくらいの費用が必要となるのでしょうか? 70万〜200万円程度が相場 夫婦墓の費用は、70万〜200万円程度が相場です。 新しくお墓を建てることになるため、一般的なお墓と比較して相場は高くなる傾向にあるようです。...
夫婦と遺族の想いに寄り添う「夫婦墓」とは?
夫婦が2人で入るためのお墓を「夫婦墓」と言います。夫婦墓は生涯を寄り添った2人の想いを形にできるだけでなく、継承を前提としないため、自分たちが旅立ったあとの「管理の不安」を解消してくれます。少子化やライフスタイルの多様化から、さまざまな形態を選べるようになったお墓。今回は、その中から夫婦墓についてご紹介します。 夫婦墓とは? 近年、注目を集めるようになったお墓のひとつが「夫婦墓(ふうふばか・めおとばか)」です。 夫婦墓とは、夫婦として過ごした2人だけが入るお墓のこと。 生前に夫婦として過ごした2人が、仏になってからも一緒にいることは縁起が良く、夫婦墓を作った家は、子々孫々にわたって幸せな家庭を築けるとも伝えられています。 継承を前提としない形が喜ばれている 夫婦墓が広く喜ばれている理由として、継承を前提としないお墓である点が挙げられます。 夫婦が2人だけで入る夫婦墓は、先祖代々受け継がれるお墓と違い、一代限りの供養が基本です。 そのため、お墓の管理や法要を寺院や自治体が請け負う「永代供養」が基本となることから、自分たちが亡くなった後のお墓の管理を心配する必要がありません。 子どもがいない方や、子どもが遠方に住んでいる方、家族や親戚への負担を心配される方にとって、夫婦墓は安心して眠ることができるお墓のスタイルと呼ぶことができるでしょう。 夫婦墓のメリットとデメリット それでは、夫婦墓についてより詳しく知るために、夫婦墓のメリットとデメリットについて見ていきましょう。 夫婦墓のメリット 夫婦墓のメリットとして、「夫婦の希望にあうお墓を選べる」点が挙げられます。 お墓に対する考え方が多様化するにつれて、自分たちの希望に添ったお墓選びも広まってきました。 デザインや場所を夫婦の希望にあわせて建てることができる点は、夫婦墓のメリットのひとつと言えるでしょう。 また、夫婦一代限りのお墓なので、寺院の場所にもこだわる必要がありません。 先祖の宗派を気にすることなく、信仰している宗教にあったお墓を選べる点も大きなメリットでしょう。 夫婦墓のデメリット 夫婦墓のデメリットには、「安置期間」に関わるものが挙げられます。 永代供養をする場合、一般的には三十三回忌や五十回忌など寺院によって安置する期間が決められています。 この期間は個別に遺骨を安置してもらえますが、期間を過ぎると合葬されることになります。 他の人たちと一緒に埋葬される合葬の形態を好まない方にはデメリットと言えるでしょう。 また、一度合葬されてしまうと、個別に遺骨を取り出すことができません。例えば、ご家族が個別の供養を望まれている場合などは注意が必要です。 夫婦墓の費用はどれくらい? お墓を建てるとなると、費用がどれくらいかかるのかは気になる項目です。 夫婦墓では、どれくらいの費用が必要となるのでしょうか? 70万〜200万円程度が相場 夫婦墓の費用は、70万〜200万円程度が相場です。 新しくお墓を建てることになるため、一般的なお墓と比較して相場は高くなる傾向にあるようです。...

分骨に込められた意味
折にふれ申しあげていることですが、昨今は故人を供養するスタイルも様々で、私どもに寄せられるご相談も多岐にわたります。中でも分骨のご要望は年々増えています。分骨とは一般的にはご遺骨の一部を他のお墓に納めることをいいますが、そこにはどのような意味があるのでしょうか。人それぞれ分骨の意味するところは異なるようです。 (なお、念のために申しあげておきますと、分骨は法律上はもちろん、宗教面でも悪いことではありません。亡くなって49日を過ぎたお骨には魂は残っておらず、残されたご遺族の思いだけがこめられています) 分骨の事情 皆様それぞれ分骨の理由をお持ちです。 故人のご遺骨をご家族のほかに兄弟姉妹のお墓に納めたい。また、ご遺骨の一部を本山納骨したり骨仏としてお納めたりする。 これにはどちらかというと故人の生前のご意志が大きく反映されるようです。 反対に、残されたご遺族の希望で分骨される場合もあります。 いつまでも手元に置いて最愛の人を感じて供養し続けたい。そこには寂しさを和らげたいという思いも込められているでしょう。人によっては、社会とのつながりが希薄で、個人が唯一の心のよりどころということもあるかもしれません。 また、もう少し現実的なこととして、ご高齢となった方にとって、遠くのお墓にお参りをすることが難しいというケースもあります。いくら故人を大切に供養したい気持ちが強くとも体がいうことを聞いてくれない。「砂埃が積もっているだろう、草も生え放題だろう」と心の中で故人に詫びているよりは、いっそ近くにお墓を建ててしまった方がよほど故人も喜ばれるでしょう。 さらには私どもが提唱しております自宅供養という方法もございます。 ますます高齢化が進む中で、このようなご事情は増えていくのではないでしょうか。 分骨は独断で行わない ほかでも述べましたとおり、分骨には法律上の定めがあります。しかし、これはしかるべき手続きに則って行えばそれで済むことです。 むしろご遺族やご親族の方々との感情的な面での相談や合意が重要となるのではないでしょうか。皆様それぞれが故人を想っていても、その想いの違いからもめ事になってしまっては、それこそ悲しいことです。 世の中がどのように変化しようとも「人が死ぬ」ということだけは変わりがないものです。だからこそ、分骨をはじめとした供養のあり方には、世の中の状況が反映されているように思えてなりません。
分骨に込められた意味
折にふれ申しあげていることですが、昨今は故人を供養するスタイルも様々で、私どもに寄せられるご相談も多岐にわたります。中でも分骨のご要望は年々増えています。分骨とは一般的にはご遺骨の一部を他のお墓に納めることをいいますが、そこにはどのような意味があるのでしょうか。人それぞれ分骨の意味するところは異なるようです。 (なお、念のために申しあげておきますと、分骨は法律上はもちろん、宗教面でも悪いことではありません。亡くなって49日を過ぎたお骨には魂は残っておらず、残されたご遺族の思いだけがこめられています) 分骨の事情 皆様それぞれ分骨の理由をお持ちです。 故人のご遺骨をご家族のほかに兄弟姉妹のお墓に納めたい。また、ご遺骨の一部を本山納骨したり骨仏としてお納めたりする。 これにはどちらかというと故人の生前のご意志が大きく反映されるようです。 反対に、残されたご遺族の希望で分骨される場合もあります。 いつまでも手元に置いて最愛の人を感じて供養し続けたい。そこには寂しさを和らげたいという思いも込められているでしょう。人によっては、社会とのつながりが希薄で、個人が唯一の心のよりどころということもあるかもしれません。 また、もう少し現実的なこととして、ご高齢となった方にとって、遠くのお墓にお参りをすることが難しいというケースもあります。いくら故人を大切に供養したい気持ちが強くとも体がいうことを聞いてくれない。「砂埃が積もっているだろう、草も生え放題だろう」と心の中で故人に詫びているよりは、いっそ近くにお墓を建ててしまった方がよほど故人も喜ばれるでしょう。 さらには私どもが提唱しております自宅供養という方法もございます。 ますます高齢化が進む中で、このようなご事情は増えていくのではないでしょうか。 分骨は独断で行わない ほかでも述べましたとおり、分骨には法律上の定めがあります。しかし、これはしかるべき手続きに則って行えばそれで済むことです。 むしろご遺族やご親族の方々との感情的な面での相談や合意が重要となるのではないでしょうか。皆様それぞれが故人を想っていても、その想いの違いからもめ事になってしまっては、それこそ悲しいことです。 世の中がどのように変化しようとも「人が死ぬ」ということだけは変わりがないものです。だからこそ、分骨をはじめとした供養のあり方には、世の中の状況が反映されているように思えてなりません。
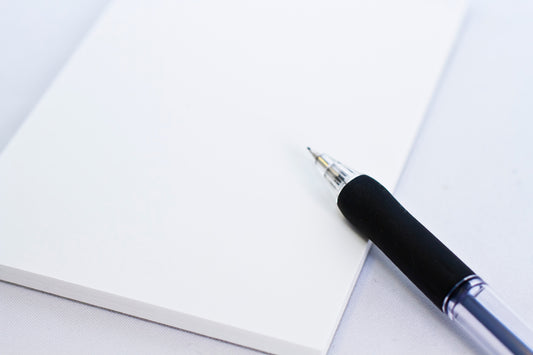
分骨に必要な手続きは?
ご遺骨を分骨して他のお墓に納めたり、あるいは手元で保管したりすることは、法律上何ら問題のあることではありません。ですが、それなりの手続きを行うことは定められています。 いつ分骨をするのか 分骨の手続きは、どの段階で分骨をするのかによって異なります。 最初から火葬場で分骨することが決まっている場合は、その旨を葬儀社や火葬場側にお伝えしておけば書類や骨壷等の準備を整えていただけます。 一方、いったんお墓に埋葬してあるお骨を分骨する場合は事情が異なります。お墓からお骨を取り出し、その一部を他のお墓に納めるわけですから、しかるべき手続きを踏まなければなりません。 後者については国の法律で定められています。 書類による証明 「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条 第五条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。 2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。 つまり、申請を受けたもの(墓地管理者等)が発行した書類をもって、お骨の取り出しと、受け入れを行うことになります。 (申請方法については特に定められてはいませんが、書面で行った方がよいでしょう。実際は申請書と証明書を兼用した書式になっていることが多いようです) これがいわゆる「分骨証明書」ですが、引用文をご覧になってお気づきのとおり、文面のどこにも「分骨証明書」という文言はありません。「埋蔵又は収蔵の事実を証する書類」と書かれているだけです。実は「分骨証明書」とは便宜上使っているだけの言葉なのですね。 そして、その書式そのものも決まったものが用意されているわけではありません。 記載内容は 現在の埋葬場所 分骨する場所 分骨する理由 などが主なようです。 ただ、自治体によっては準備しているところもありますので、分骨をお考えの方は、いちどお住まいの役所にお問い合わせをされた方がよいでしょう。 自宅供養の場合 ところで、分骨後の納め先が他のお墓ではなくご自宅での保管の場合はどうすればよいでしょうか。上記の文面からはそこまでのことは読み取れないですね。 いずれにせよお墓から取り出す際に申請が必要となりますし、もしかしたらご事情が変わって再度お墓へ納骨するということも考えて、分骨証明書を作成しておくことをおすすめします。
分骨に必要な手続きは?
ご遺骨を分骨して他のお墓に納めたり、あるいは手元で保管したりすることは、法律上何ら問題のあることではありません。ですが、それなりの手続きを行うことは定められています。 いつ分骨をするのか 分骨の手続きは、どの段階で分骨をするのかによって異なります。 最初から火葬場で分骨することが決まっている場合は、その旨を葬儀社や火葬場側にお伝えしておけば書類や骨壷等の準備を整えていただけます。 一方、いったんお墓に埋葬してあるお骨を分骨する場合は事情が異なります。お墓からお骨を取り出し、その一部を他のお墓に納めるわけですから、しかるべき手続きを踏まなければなりません。 後者については国の法律で定められています。 書類による証明 「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条 第五条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。 2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。 つまり、申請を受けたもの(墓地管理者等)が発行した書類をもって、お骨の取り出しと、受け入れを行うことになります。 (申請方法については特に定められてはいませんが、書面で行った方がよいでしょう。実際は申請書と証明書を兼用した書式になっていることが多いようです) これがいわゆる「分骨証明書」ですが、引用文をご覧になってお気づきのとおり、文面のどこにも「分骨証明書」という文言はありません。「埋蔵又は収蔵の事実を証する書類」と書かれているだけです。実は「分骨証明書」とは便宜上使っているだけの言葉なのですね。 そして、その書式そのものも決まったものが用意されているわけではありません。 記載内容は 現在の埋葬場所 分骨する場所 分骨する理由 などが主なようです。 ただ、自治体によっては準備しているところもありますので、分骨をお考えの方は、いちどお住まいの役所にお問い合わせをされた方がよいでしょう。 自宅供養の場合 ところで、分骨後の納め先が他のお墓ではなくご自宅での保管の場合はどうすればよいでしょうか。上記の文面からはそこまでのことは読み取れないですね。 いずれにせよお墓から取り出す際に申請が必要となりますし、もしかしたらご事情が変わって再度お墓へ納骨するということも考えて、分骨証明書を作成しておくことをおすすめします。










