手元供養に関する記事

手元供養のススメ
お彼岸を過ぎても寒い日が続きますが、 春はしっかりやってきています。 さて、お客様からメールをいただきましたので、ご紹介いたします。 T様はご遺骨の一部をカロートペンダントの「グラスシリンダー・いぶし銀」に 納めておられます。 「平日はYシャツの内側になるように装着しており、 比較的堅い会社勤めの身でも常に一緒にいられる気持ちでいられます。 出張も多いので、より一層助かっています。」 「ブレスレットには遺髪を封入させていただいております。 こちらは就業中は身に付けられませんが、それ以外は常時装着させていただいております。」 「お墓に入ってもどうせ年に1.2回しかお参りにはいけない」 「年をとればそれも辛くなる」と故人が生前申しておりました。 手元供養を選択したことで毎日どこでも供養できます。 ありがとうございました。 「お墓はあるのですが、入りたくないという故人の意思を尊重し、 手元供養という選択もできること」 「遺骨がどこにあろうとも故人に想いを馳せることはできますが、 手元で供養することでより一層共にいられる感情を得られること」などは もっと広められても良いと感じています。 とメール下さいました。 T様、ありがとうございました。 従来のご供養のあり方だけでなく、もっと自由に供養する方法があるということを みなさまに知っていただければ、心休まる方も多いのではないかと存じます。 もっともっと、このような供養のあり方を知っていただく努力をしないといけないですね。 みなさまの心安らぐお手伝いをすること! 改めて激励の「喝」をいただいた気持ちです。 ありがとうございました。
手元供養のススメ
お彼岸を過ぎても寒い日が続きますが、 春はしっかりやってきています。 さて、お客様からメールをいただきましたので、ご紹介いたします。 T様はご遺骨の一部をカロートペンダントの「グラスシリンダー・いぶし銀」に 納めておられます。 「平日はYシャツの内側になるように装着しており、 比較的堅い会社勤めの身でも常に一緒にいられる気持ちでいられます。 出張も多いので、より一層助かっています。」 「ブレスレットには遺髪を封入させていただいております。 こちらは就業中は身に付けられませんが、それ以外は常時装着させていただいております。」 「お墓に入ってもどうせ年に1.2回しかお参りにはいけない」 「年をとればそれも辛くなる」と故人が生前申しておりました。 手元供養を選択したことで毎日どこでも供養できます。 ありがとうございました。 「お墓はあるのですが、入りたくないという故人の意思を尊重し、 手元供養という選択もできること」 「遺骨がどこにあろうとも故人に想いを馳せることはできますが、 手元で供養することでより一層共にいられる感情を得られること」などは もっと広められても良いと感じています。 とメール下さいました。 T様、ありがとうございました。 従来のご供養のあり方だけでなく、もっと自由に供養する方法があるということを みなさまに知っていただければ、心休まる方も多いのではないかと存じます。 もっともっと、このような供養のあり方を知っていただく努力をしないといけないですね。 みなさまの心安らぐお手伝いをすること! 改めて激励の「喝」をいただいた気持ちです。 ありがとうございました。

手元供養~49日を過ぎてもご遺骨とともに~
手元供養〜49日を過ぎてもご遺骨とともに〜 一般的に納骨をする49日は、手元供養を考えるきっかけになるかもしれません。手元供養は、納骨の日が近づいても離れがたい思いや、寂しさが残って納骨が辛いと苦しむ思いを和らげる供養といえるからです。 49日(四十九日)とは? 仏教では輪廻転生の思想から、人が亡くなってから49日の間は、再び生まれ変わるまでの準備期間であるとされています。 仏教において、人が生まれ変わって行く先の世界が“来世”。来世は地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人間道・天上道の「六道」と呼ばれる、6つの階層の行き先に別れています。 なかでも極楽として知られているのが、最上階の天上道。人の魂は生前の行いによって来世での行先が決まり、この六道の中でふさわしい世界に生まれ変わっていくのだそうです。 そして亡くなってから49日間が、閻魔大王によってこの行き先を決めてもらうための期間。閻魔大王は7日ごとに故人の生前の行いを厳しく吟味し、49日目に裁きを下します。 遺族の祈りが逝き先を変える この49日の間に家族が祈りを捧げれば、それが故人の善行として追加され、故人が極楽へ行く助けとなるとされています。遺骨を家に置いて別れを惜しむとともに極楽への成仏を祈るのは、一種の手元供養と言えるかもしれません。 とくに最初の吟味が行われる7日目(初七日/しょなのか)と、裁定が下る49日目(四十九日/しじゅうくにち)を大切な区切りの日として法要を行います。 49日というのは、仏教において故人の魂が来世へと旅立つ日であり、遺族が故人に改めて別れを告げる区切りの日という意味があるのです。 割りきれない心を癒す手元供養 「旅立ちの日」「区切りの日」といった意味合いから、一般的には故人が亡くなってから49日目、つまり四十九日の法要の際にお墓への納骨も行われます。しかし「ここで区切り」と言われても、実際に遺された人の心は、そんなに簡単に割りきれるものではありません。 49日間ずっとそばにあった遺骨が、いよいよお墓へ納骨されるという段になって、再び深い悲しみと喪失感に襲われてしまう人も多いのです。 愛する人が残した“命の証”とも言える遺骨に対して、「故人の身代わりとして、いつまでもそばに置いておきたい」「ずっと見守ってほしい」といった、離れがたい想いを遺族が抱くのは、ごく当たり前のことでしょう。 その想いは、「手元供養」という形によって叶えることができます。手元供養は、故人の遺骨を身近におくことによって、遺された人の心を癒すための新しい供養方法なのです。 いつまでもご遺骨をお手元に 遺骨の一部を取り分けて(“分骨”といいます)、自宅など身近においてお参りするのが手元供養。 お墓へ納骨する前に分骨して手元供養にすれば、49日を過ぎても遺族と遺骨とが引き離されることはありません。故人の思い出に励まされて、遺された人も次の一歩を踏み出していけるでしょう。 なお、分骨や遺骨を手元に置くことは、宗教的にも法律的にも何ら問題はありませんのでご安心ください。 現代では手元供養の広がりにあわせて、製品も多様なタイプのものが揃っています。その中から自分のライフスタイルに合わせてぴったりの品を選び、大切な方を偲べます。 好きな場所に飾り、好きなときにゆっくりお参りできる”ミニ骨壷”、遺骨を入れて身につけることで故人といつも一緒にいられる”遺骨ペンダント”。49日を過ぎても近くに遺骨があれば、寂しさも次第に癒えていくでしょう。 より身近な手元供養〜遺骨ペンダント5選 愛しさや寂しさを癒すために、肌身離さず一緒にいられるのが遺骨ペンダント。大切な人への想いが強いからこそ、お骨の入れ物をペンダントにしたいという方が増えています。 美しく遺骨を閉じこめるペンダント「アズール(ハート)」 光のきらめきのように、小さなあぶくのように、遺骨をエナメル樹脂で美しく閉じこめるアズールシリーズ。中でもハートペンダントは、大切な人への想いや愛を表す形の手元供養品として人気です。 台座は上品なシルバーで、エナメルの色は5色の中から選べます。誕生石やダイヤモンドをあしらったり、名前を入れたりで、よりオリジナルな遺骨ペンダントに。 美しく遺骨があしらわれたペンダントは、49日が終わった後も故人を身近に感じていたいという方にぴったりです。 >遺骨ペンダント「アズール(ハート)」の商品詳細はこちら 大切な人と再び時を刻むペンダント「アワーグラス」(シルバー)...
手元供養~49日を過ぎてもご遺骨とともに~
手元供養〜49日を過ぎてもご遺骨とともに〜 一般的に納骨をする49日は、手元供養を考えるきっかけになるかもしれません。手元供養は、納骨の日が近づいても離れがたい思いや、寂しさが残って納骨が辛いと苦しむ思いを和らげる供養といえるからです。 49日(四十九日)とは? 仏教では輪廻転生の思想から、人が亡くなってから49日の間は、再び生まれ変わるまでの準備期間であるとされています。 仏教において、人が生まれ変わって行く先の世界が“来世”。来世は地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人間道・天上道の「六道」と呼ばれる、6つの階層の行き先に別れています。 なかでも極楽として知られているのが、最上階の天上道。人の魂は生前の行いによって来世での行先が決まり、この六道の中でふさわしい世界に生まれ変わっていくのだそうです。 そして亡くなってから49日間が、閻魔大王によってこの行き先を決めてもらうための期間。閻魔大王は7日ごとに故人の生前の行いを厳しく吟味し、49日目に裁きを下します。 遺族の祈りが逝き先を変える この49日の間に家族が祈りを捧げれば、それが故人の善行として追加され、故人が極楽へ行く助けとなるとされています。遺骨を家に置いて別れを惜しむとともに極楽への成仏を祈るのは、一種の手元供養と言えるかもしれません。 とくに最初の吟味が行われる7日目(初七日/しょなのか)と、裁定が下る49日目(四十九日/しじゅうくにち)を大切な区切りの日として法要を行います。 49日というのは、仏教において故人の魂が来世へと旅立つ日であり、遺族が故人に改めて別れを告げる区切りの日という意味があるのです。 割りきれない心を癒す手元供養 「旅立ちの日」「区切りの日」といった意味合いから、一般的には故人が亡くなってから49日目、つまり四十九日の法要の際にお墓への納骨も行われます。しかし「ここで区切り」と言われても、実際に遺された人の心は、そんなに簡単に割りきれるものではありません。 49日間ずっとそばにあった遺骨が、いよいよお墓へ納骨されるという段になって、再び深い悲しみと喪失感に襲われてしまう人も多いのです。 愛する人が残した“命の証”とも言える遺骨に対して、「故人の身代わりとして、いつまでもそばに置いておきたい」「ずっと見守ってほしい」といった、離れがたい想いを遺族が抱くのは、ごく当たり前のことでしょう。 その想いは、「手元供養」という形によって叶えることができます。手元供養は、故人の遺骨を身近におくことによって、遺された人の心を癒すための新しい供養方法なのです。 いつまでもご遺骨をお手元に 遺骨の一部を取り分けて(“分骨”といいます)、自宅など身近においてお参りするのが手元供養。 お墓へ納骨する前に分骨して手元供養にすれば、49日を過ぎても遺族と遺骨とが引き離されることはありません。故人の思い出に励まされて、遺された人も次の一歩を踏み出していけるでしょう。 なお、分骨や遺骨を手元に置くことは、宗教的にも法律的にも何ら問題はありませんのでご安心ください。 現代では手元供養の広がりにあわせて、製品も多様なタイプのものが揃っています。その中から自分のライフスタイルに合わせてぴったりの品を選び、大切な方を偲べます。 好きな場所に飾り、好きなときにゆっくりお参りできる”ミニ骨壷”、遺骨を入れて身につけることで故人といつも一緒にいられる”遺骨ペンダント”。49日を過ぎても近くに遺骨があれば、寂しさも次第に癒えていくでしょう。 より身近な手元供養〜遺骨ペンダント5選 愛しさや寂しさを癒すために、肌身離さず一緒にいられるのが遺骨ペンダント。大切な人への想いが強いからこそ、お骨の入れ物をペンダントにしたいという方が増えています。 美しく遺骨を閉じこめるペンダント「アズール(ハート)」 光のきらめきのように、小さなあぶくのように、遺骨をエナメル樹脂で美しく閉じこめるアズールシリーズ。中でもハートペンダントは、大切な人への想いや愛を表す形の手元供養品として人気です。 台座は上品なシルバーで、エナメルの色は5色の中から選べます。誕生石やダイヤモンドをあしらったり、名前を入れたりで、よりオリジナルな遺骨ペンダントに。 美しく遺骨があしらわれたペンダントは、49日が終わった後も故人を身近に感じていたいという方にぴったりです。 >遺骨ペンダント「アズール(ハート)」の商品詳細はこちら 大切な人と再び時を刻むペンダント「アワーグラス」(シルバー)...

お墓参りに行けない方へ。「手元供養」を始めませんか?
親族が集う年末年始、お墓参りに行かれる方も多いことと思います。故郷から離れて暮らす方にとっては、故人に想いをはせる貴重なひと時と言えるかもしれません。 できることなら、普段から故人を偲ぶ気持ちは忘れずにいたいもの。そんな想いを持つ方々に、手元供養という供養の形があることを、ぜひ知っていただきたいと思っています。 「手元供養」という供養の形 手元供養とは、形にとらわれず故人を偲ぶ自由で新しい供養の形です。毎日の生活の中で、ささやかな祈りの時間を設けたり、遺骨ペンダントを身に着けたりとそのやり方も人それぞれ。 各人が自分にふさわしいと思うやり方で、故人への想いをつむぎます。 注目を集めている手元供養 手元供養は、生活環境の変化から注目される機会が増えています。 近年では、お墓のある故郷を離れ、遠方に住居をかまえる方が珍しくなくなりました。また、仏壇を置く和室が少なくなったことも、手元供養が注目される理由の一つ。 手元供養品はオシャレなデザインのものも多く、洋風のインテリアにも違和感を与えることなく溶け込みます。時代のニーズに合っているからこそ、新しい供養方法として多くの方々から注目されているのです。 日々の生活に安らぎが生まれる なにかと時間に追われている現代。日々の生活に忙殺されて、息苦しくなっている方もいることでしょう。日常の中に心安らぐ時間がないと、私たちの心はどんどんやせ細ってしまいます。 もしあなたが生き苦しさを感じているのなら手元供養を始めてみませんか?故人を偲び、想いを馳せる。それは、かけがえのない心安らぐひと時です。 手元供養をはじめるには 手元供養を始めるのに、形式ばった儀式や取り決めなどは一切必要ありません。 必要なのは、故人を偲ぶ気持ちと毎日の生活の中で祈りを捧げる空間だけ。未来創想では、祈りの空間作りに彩りを添える、ささやかな供養品をご用意しております。 オシャレなミニ仏壇 従来の仏壇は宗教色の強いものが一般的でしたが、未来創想のミニ仏壇は洋風のインテリアにもなじみやすい洗練されたデザインが特徴です。リビングの雰囲気をくずすことなく、ささやかな祈りの空間が作れます。 >ミニ仏壇 の商品一覧はこちら ミニ骨壷 ミニ骨壷は、手のひらサイズのオシャレな骨壷。色鮮やかなガラス製や、温もりを感じる陶器製のものなど、個性あふれるミニ骨壷を多数ご用意しています。 >ミニ骨壷 の商品一覧はこちら 遺骨ペンダント 遺骨ペンダントは、愛する人をいつでも身近に感じさせてくれるアクセサリー。抵抗感を抱かれる方もいるかもしれませんが、遺骨ペンダントは法律的にも宗教的にも、なんら問題あるものではありません。 故人とのつながりを持ち続けたいと思うのであれば、その想いを大切にするようにしてください。 >遺骨ペンダント の商品一覧はこちら 悲しみが少しでも癒えるように 手元供養は、日々の生活の中で故人を偲べる自由で新しい供養の形です。私たち未来創想は、手元供養という言葉が広がる以前から、残された人の心の支えとなるような商品づくりに取り組んでいます。...
お墓参りに行けない方へ。「手元供養」を始めませんか?
親族が集う年末年始、お墓参りに行かれる方も多いことと思います。故郷から離れて暮らす方にとっては、故人に想いをはせる貴重なひと時と言えるかもしれません。 できることなら、普段から故人を偲ぶ気持ちは忘れずにいたいもの。そんな想いを持つ方々に、手元供養という供養の形があることを、ぜひ知っていただきたいと思っています。 「手元供養」という供養の形 手元供養とは、形にとらわれず故人を偲ぶ自由で新しい供養の形です。毎日の生活の中で、ささやかな祈りの時間を設けたり、遺骨ペンダントを身に着けたりとそのやり方も人それぞれ。 各人が自分にふさわしいと思うやり方で、故人への想いをつむぎます。 注目を集めている手元供養 手元供養は、生活環境の変化から注目される機会が増えています。 近年では、お墓のある故郷を離れ、遠方に住居をかまえる方が珍しくなくなりました。また、仏壇を置く和室が少なくなったことも、手元供養が注目される理由の一つ。 手元供養品はオシャレなデザインのものも多く、洋風のインテリアにも違和感を与えることなく溶け込みます。時代のニーズに合っているからこそ、新しい供養方法として多くの方々から注目されているのです。 日々の生活に安らぎが生まれる なにかと時間に追われている現代。日々の生活に忙殺されて、息苦しくなっている方もいることでしょう。日常の中に心安らぐ時間がないと、私たちの心はどんどんやせ細ってしまいます。 もしあなたが生き苦しさを感じているのなら手元供養を始めてみませんか?故人を偲び、想いを馳せる。それは、かけがえのない心安らぐひと時です。 手元供養をはじめるには 手元供養を始めるのに、形式ばった儀式や取り決めなどは一切必要ありません。 必要なのは、故人を偲ぶ気持ちと毎日の生活の中で祈りを捧げる空間だけ。未来創想では、祈りの空間作りに彩りを添える、ささやかな供養品をご用意しております。 オシャレなミニ仏壇 従来の仏壇は宗教色の強いものが一般的でしたが、未来創想のミニ仏壇は洋風のインテリアにもなじみやすい洗練されたデザインが特徴です。リビングの雰囲気をくずすことなく、ささやかな祈りの空間が作れます。 >ミニ仏壇 の商品一覧はこちら ミニ骨壷 ミニ骨壷は、手のひらサイズのオシャレな骨壷。色鮮やかなガラス製や、温もりを感じる陶器製のものなど、個性あふれるミニ骨壷を多数ご用意しています。 >ミニ骨壷 の商品一覧はこちら 遺骨ペンダント 遺骨ペンダントは、愛する人をいつでも身近に感じさせてくれるアクセサリー。抵抗感を抱かれる方もいるかもしれませんが、遺骨ペンダントは法律的にも宗教的にも、なんら問題あるものではありません。 故人とのつながりを持ち続けたいと思うのであれば、その想いを大切にするようにしてください。 >遺骨ペンダント の商品一覧はこちら 悲しみが少しでも癒えるように 手元供養は、日々の生活の中で故人を偲べる自由で新しい供養の形です。私たち未来創想は、手元供養という言葉が広がる以前から、残された人の心の支えとなるような商品づくりに取り組んでいます。...

分骨の手続きについて~手元供養の知識
ご遺骨を分骨して手元において保管、供養するというだけであれば、とくに手続きは必要ありません。ただ、その手元供養をしているご遺骨を、改めてお墓に納骨するという場合には「分骨証明書」が必要です。 ここでは、分骨の手続きについてご説明させていただきます。 分骨の方法によって異なる手続き 亡くなった方のご遺骨を分骨することは、法律上何ら問題のあることではありません。近年では、手元供養の広まりにともなって、分骨を希望される方も多くなりました。 分骨したご遺骨を手元供養するだけであれば、とくにこれといった手続きは必要ありませんが、後に何らかの事情でその手元のご遺骨をお墓に納めることになった場合、「分骨証明書」などの書類が必要になります。 分骨についての手続きは、分骨の方法によって次のように異なります。 火葬場で分骨する場合の手続き 火葬場で分骨する場合は、火葬場の窓口で分骨証明書を必要な枚数発行していただきます。その後、火葬場の方で分骨していただいたお骨を各自で受けとります。 分骨することが決まっている場合は、その旨を葬儀社や火葬場側に事前に伝えておくと、分骨に必要な書類の発行がスムーズです。手元供養のための骨壷なども予め準備しておけば、当日お骨を納めて持ち帰ることも可能です。 お墓からご遺骨を取り出して分骨する場合の手続き すでにお墓に納められてしまっているご遺骨を分骨する場合は、分骨証明書は墓地の管理者から発行していただくことになります。 その後、お墓からご遺骨を取り出して、必要なだけ分骨します。 分骨証明書とは? 上記いずれの場合にも、必要となる「分骨証明書」ですが、これはそのご遺骨が“どなたのものであるか”を証明する書類です。分骨したご遺骨を別のお墓に納骨するという場合は、分骨証明書を新たなご遺骨の納め先となる墓地の管理者へ提出します。 現時点で手元供養をご検討の方も、今後、ご遺骨をお墓に納めることがあるかもしれません。その際には分骨証明書が必要となりますので、大切に保管しておきましょう。 いつかは訪れる日に備えて 大切な誰かを亡くした悲しみの中で、さまざまな手続きなどに追われるのは大変なことです。分骨などに必要な手続きについて事前に知っておくことは、誰にもいつか訪れるその日を、安心して迎えるための備えとなるでしょう。 こうした手続きについての疑問・お悩みの際は、ぜひお気軽に私たち未来創想へご相談いただければと思います。
分骨の手続きについて~手元供養の知識
ご遺骨を分骨して手元において保管、供養するというだけであれば、とくに手続きは必要ありません。ただ、その手元供養をしているご遺骨を、改めてお墓に納骨するという場合には「分骨証明書」が必要です。 ここでは、分骨の手続きについてご説明させていただきます。 分骨の方法によって異なる手続き 亡くなった方のご遺骨を分骨することは、法律上何ら問題のあることではありません。近年では、手元供養の広まりにともなって、分骨を希望される方も多くなりました。 分骨したご遺骨を手元供養するだけであれば、とくにこれといった手続きは必要ありませんが、後に何らかの事情でその手元のご遺骨をお墓に納めることになった場合、「分骨証明書」などの書類が必要になります。 分骨についての手続きは、分骨の方法によって次のように異なります。 火葬場で分骨する場合の手続き 火葬場で分骨する場合は、火葬場の窓口で分骨証明書を必要な枚数発行していただきます。その後、火葬場の方で分骨していただいたお骨を各自で受けとります。 分骨することが決まっている場合は、その旨を葬儀社や火葬場側に事前に伝えておくと、分骨に必要な書類の発行がスムーズです。手元供養のための骨壷なども予め準備しておけば、当日お骨を納めて持ち帰ることも可能です。 お墓からご遺骨を取り出して分骨する場合の手続き すでにお墓に納められてしまっているご遺骨を分骨する場合は、分骨証明書は墓地の管理者から発行していただくことになります。 その後、お墓からご遺骨を取り出して、必要なだけ分骨します。 分骨証明書とは? 上記いずれの場合にも、必要となる「分骨証明書」ですが、これはそのご遺骨が“どなたのものであるか”を証明する書類です。分骨したご遺骨を別のお墓に納骨するという場合は、分骨証明書を新たなご遺骨の納め先となる墓地の管理者へ提出します。 現時点で手元供養をご検討の方も、今後、ご遺骨をお墓に納めることがあるかもしれません。その際には分骨証明書が必要となりますので、大切に保管しておきましょう。 いつかは訪れる日に備えて 大切な誰かを亡くした悲しみの中で、さまざまな手続きなどに追われるのは大変なことです。分骨などに必要な手続きについて事前に知っておくことは、誰にもいつか訪れるその日を、安心して迎えるための備えとなるでしょう。 こうした手続きについての疑問・お悩みの際は、ぜひお気軽に私たち未来創想へご相談いただければと思います。
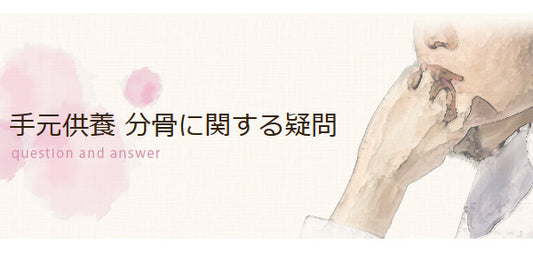
手元供養で分骨する際のご質問にお答えします
ご遺骨を分骨してご自宅など身近に置き、故人を偲ぶ手元供養。近年ますます注目を集めており、手元供養についてのお問い合わせも数多くいただくようになりました。 そうした中でも、とりわけよくいただくのが分骨についてのご質問です。分骨には、人によっても地域によっても様々な説や言い伝えがあり、手元供養をお考えのご遺族の中には、思い悩んでしまわれる方も少なくありません。 ここでは、そんな分骨についてのご質問にお答えしていきたいと思います。 分骨に関する疑問1.「分骨すると成仏できない?」 分骨についてもっとも多いのが、ご親戚やご友人から「“分骨すると成仏できない”と言われたけれど大丈夫でしょうか?」というご質問です。同様に“魂が分裂してしまう”、“あの世で五体がそろわない”などとも言われますが、いずれにしてもこのようなことを聞かれたご遺族のご心配は察して余りあるものでしょう。 結論から言いますと、これらはすべて根拠のない迷信であり、心配される必要は全くありません。 分骨は、昔から様々な宗教において、尊い行為として広く行われてきたことです。例えば仏教では、お釈迦様のご遺骨は「仏舎利」として分骨され、世界各地の寺院で大切にお祀りされています。またキリスト教においても、「聖遺骨」と呼ばれる諸聖人の遺骨の一部が、様々な場所で人々の敬意を集めています。 こうしたことからもお判りいただけるように、手元供養のために分骨することが、故人の魂に災いをもたらすなどということは決してないのです。もちろん法律においても何ら問題ありませんので、どうぞご安心ください。 分骨に関する疑問2.「分骨のタイミングは?」 分骨のタイミングとしては、ご家族の場合、火葬の後ご自宅へお戻りになられたときがもっとも多いようです。ご一緒に戻られた故人の骨壷から、手元供養のためのご遺骨を取り分けます。また、火葬のお骨上げの時点で、分骨してとっておかれる方もいらっしゃいます。 すでにお墓などに納骨されてしまっているご遺骨の場合は、墓地管理者に了解を得た上で、お墓の中の骨壷から分骨されるということになります。 分骨に関する疑問3.「分骨証明書は必要?」 分骨証明書は、分骨したご遺骨を別のお墓に納める際に必要な書類です。したがって、手元供養のために分骨した場合は、基本的には分骨証明書は必要ありません。 しかしながら、後々事情が変わって納骨するという場合も考えられますので、そのときのために、可能であるならば分骨証明書を用意しておかれることをおすすめします。 分骨に関する疑問4.「分骨した後の残りの遺骨は?」 分骨して残された分のご遺骨については、あらためて行く先を決めておかれる必要があります。 お墓がある場合は、通常通りそちらへ納骨されるのが一般的です。またお墓がない場合にも、本山納骨、合祀永代供養、散骨などの自然葬といった様々な選択肢がありますので、ご家族で充分にご相談の上、故人にふさわしい行き先を選んであげていただくとよいでしょう。 また、分骨して手元供養にしたご遺骨も、「落ち着いたら他のお骨と一緒にお墓に納める」「自分の死後に自分のお骨とともに散骨する」など、あらかじめその行く末を決めておかれると安心です。 おわりに 分骨や手元供養についての考え方は人それぞれ。ご家族の中でも、意見が異なることもあるでしょう。しかし、故人を想う心はどなたも同じです。故人のためにどのようなかたちでお弔いしていくのか、まずはご遺族でよく話し合われることが肝心です。 ご遺族の全員が悲しみから立ち直り、それぞれの人生をしっかりと歩いていかれることで、故人もお喜びになると思います。 分骨、手元供養に関するさらなるご質問は、ぜひ私たちへお問い合わせください。ご遺族皆様の心に寄り添い、様々なお手伝いをさせていただくこと、それが未来創想の使命です。
手元供養で分骨する際のご質問にお答えします
ご遺骨を分骨してご自宅など身近に置き、故人を偲ぶ手元供養。近年ますます注目を集めており、手元供養についてのお問い合わせも数多くいただくようになりました。 そうした中でも、とりわけよくいただくのが分骨についてのご質問です。分骨には、人によっても地域によっても様々な説や言い伝えがあり、手元供養をお考えのご遺族の中には、思い悩んでしまわれる方も少なくありません。 ここでは、そんな分骨についてのご質問にお答えしていきたいと思います。 分骨に関する疑問1.「分骨すると成仏できない?」 分骨についてもっとも多いのが、ご親戚やご友人から「“分骨すると成仏できない”と言われたけれど大丈夫でしょうか?」というご質問です。同様に“魂が分裂してしまう”、“あの世で五体がそろわない”などとも言われますが、いずれにしてもこのようなことを聞かれたご遺族のご心配は察して余りあるものでしょう。 結論から言いますと、これらはすべて根拠のない迷信であり、心配される必要は全くありません。 分骨は、昔から様々な宗教において、尊い行為として広く行われてきたことです。例えば仏教では、お釈迦様のご遺骨は「仏舎利」として分骨され、世界各地の寺院で大切にお祀りされています。またキリスト教においても、「聖遺骨」と呼ばれる諸聖人の遺骨の一部が、様々な場所で人々の敬意を集めています。 こうしたことからもお判りいただけるように、手元供養のために分骨することが、故人の魂に災いをもたらすなどということは決してないのです。もちろん法律においても何ら問題ありませんので、どうぞご安心ください。 分骨に関する疑問2.「分骨のタイミングは?」 分骨のタイミングとしては、ご家族の場合、火葬の後ご自宅へお戻りになられたときがもっとも多いようです。ご一緒に戻られた故人の骨壷から、手元供養のためのご遺骨を取り分けます。また、火葬のお骨上げの時点で、分骨してとっておかれる方もいらっしゃいます。 すでにお墓などに納骨されてしまっているご遺骨の場合は、墓地管理者に了解を得た上で、お墓の中の骨壷から分骨されるということになります。 分骨に関する疑問3.「分骨証明書は必要?」 分骨証明書は、分骨したご遺骨を別のお墓に納める際に必要な書類です。したがって、手元供養のために分骨した場合は、基本的には分骨証明書は必要ありません。 しかしながら、後々事情が変わって納骨するという場合も考えられますので、そのときのために、可能であるならば分骨証明書を用意しておかれることをおすすめします。 分骨に関する疑問4.「分骨した後の残りの遺骨は?」 分骨して残された分のご遺骨については、あらためて行く先を決めておかれる必要があります。 お墓がある場合は、通常通りそちらへ納骨されるのが一般的です。またお墓がない場合にも、本山納骨、合祀永代供養、散骨などの自然葬といった様々な選択肢がありますので、ご家族で充分にご相談の上、故人にふさわしい行き先を選んであげていただくとよいでしょう。 また、分骨して手元供養にしたご遺骨も、「落ち着いたら他のお骨と一緒にお墓に納める」「自分の死後に自分のお骨とともに散骨する」など、あらかじめその行く末を決めておかれると安心です。 おわりに 分骨や手元供養についての考え方は人それぞれ。ご家族の中でも、意見が異なることもあるでしょう。しかし、故人を想う心はどなたも同じです。故人のためにどのようなかたちでお弔いしていくのか、まずはご遺族でよく話し合われることが肝心です。 ご遺族の全員が悲しみから立ち直り、それぞれの人生をしっかりと歩いていかれることで、故人もお喜びになると思います。 分骨、手元供養に関するさらなるご質問は、ぜひ私たちへお問い合わせください。ご遺族皆様の心に寄り添い、様々なお手伝いをさせていただくこと、それが未来創想の使命です。
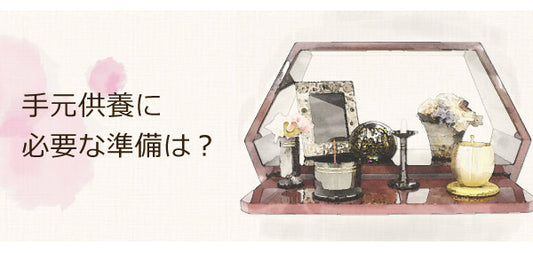
手元供養に必要な準備は?
既存のしきたりや形式にとらわれることなく自由に故人を偲ぶ「手元供養」は、現在、幅広い層の方々から認めていただくようになりました。手元供養に関するご質問もたくさんお寄せいただいておりますが、中でも近年多くなっているのが「手元供養の際の実際の準備」についてのお問い合わせです。 そこで、手元供養の準備についてのご質問を、まとめてご紹介させていただきたいと思います。 手元供養って何を準備したらいいの? 手元供養では、亡くなった方のお骨を分骨し、手元において供養しますので、分骨したお骨を入れる「容器」が必要となります。 この容器については基本的にとくに決まりはないのですが、大切なお骨を安全・安心に保管していただくためには、やはり「手元供養品」と呼ばれる専用のものをおすすめしております。 「手元供養品」には、お骨を入れて身につける「遺骨ペンダント」や、ご自宅に飾りやすくデザイン性の高い「ミニ骨壷(コアボトル)」など、多彩なスタイルのものが数多く用意されていまので、それぞれのお好みに合わせてご自由にお選びいただけます。 手元供養品はいつ準備するの? 手元供養品を準備するタイミングは、その手元供養品に「どなたのお骨を納めるのか?」によって違います。 亡くなったご家族など、大切な相手のお骨を納める場合 ご家族のどなたかなど、ご自身にとって大切な方のご遺骨を納めるという場合、お亡くなりになった後に手元供養品を探されることが多いようです。 一般的な仏式のご葬儀では、四十九日の法要の際に合わせてお骨をお墓へ納骨されることが多いので、この時までに手元供養品をご準備されるとよいでしょう。 ご自分の死後、ご自身のお骨を納めてもらう場合 様々な事情からお墓を建立されない方も多くなりましたが、そうした方がご家族のことを考えて、お墓の代わりとして手元供養を選ばれる場合があります。 このような場合には、生前にご自分の死生観や供養観、“こう弔ってほしい”というご希望などに合わせて、手元供養品をご準備いただくことができます。 手元供養品を生前に準備しても大丈夫? 手元供養品を生前に準備することを、“なんとなく縁起が悪いような気がして…”とためらわれる方もいらっしゃいます。同じように生前にお墓を建てたり、お仏壇を購入されたりする際にも、縁起が悪いと言われることは少なくないようです。 しかし実は、これらはとくに根拠のない迷信で、まったく気にされる必要はありません。むしろ、生前にお墓を建てることは「寿陵(じゅりょう)」、お仏壇を買うことは「寿院(じゅいん)」とそれぞれ呼ばれ、とても縁起の良いこととされているのです。 こうしたことから、手元供養品も生前に準備することには何も問題ないと言って間違いないでしょう。 また現実的な側面においても、生前からご自分でその行く末について事前に決めておかれることは、ご自身とご家族の安心を得られるというメリットがあります。誰しもいつかは必ず迎えるその日のために、ご家族と一緒に様々な準備について考えてみられてはいかがでしょうか。 おわりに 大切な人を亡くした深い悲しみの中で。 あるいはやがて訪れる別れの日を考えて。 手元供養の準備をされる方のご事情や、想いは人それぞれです。手元供養品などの準備についてお困りのことやご質問などは、ぜひお気軽に未来創想へお問い合わせください。お一人お一人のお声に耳を傾け、よりご満足いただけるよう、様々なご提案をさせていただきます。
手元供養に必要な準備は?
既存のしきたりや形式にとらわれることなく自由に故人を偲ぶ「手元供養」は、現在、幅広い層の方々から認めていただくようになりました。手元供養に関するご質問もたくさんお寄せいただいておりますが、中でも近年多くなっているのが「手元供養の際の実際の準備」についてのお問い合わせです。 そこで、手元供養の準備についてのご質問を、まとめてご紹介させていただきたいと思います。 手元供養って何を準備したらいいの? 手元供養では、亡くなった方のお骨を分骨し、手元において供養しますので、分骨したお骨を入れる「容器」が必要となります。 この容器については基本的にとくに決まりはないのですが、大切なお骨を安全・安心に保管していただくためには、やはり「手元供養品」と呼ばれる専用のものをおすすめしております。 「手元供養品」には、お骨を入れて身につける「遺骨ペンダント」や、ご自宅に飾りやすくデザイン性の高い「ミニ骨壷(コアボトル)」など、多彩なスタイルのものが数多く用意されていまので、それぞれのお好みに合わせてご自由にお選びいただけます。 手元供養品はいつ準備するの? 手元供養品を準備するタイミングは、その手元供養品に「どなたのお骨を納めるのか?」によって違います。 亡くなったご家族など、大切な相手のお骨を納める場合 ご家族のどなたかなど、ご自身にとって大切な方のご遺骨を納めるという場合、お亡くなりになった後に手元供養品を探されることが多いようです。 一般的な仏式のご葬儀では、四十九日の法要の際に合わせてお骨をお墓へ納骨されることが多いので、この時までに手元供養品をご準備されるとよいでしょう。 ご自分の死後、ご自身のお骨を納めてもらう場合 様々な事情からお墓を建立されない方も多くなりましたが、そうした方がご家族のことを考えて、お墓の代わりとして手元供養を選ばれる場合があります。 このような場合には、生前にご自分の死生観や供養観、“こう弔ってほしい”というご希望などに合わせて、手元供養品をご準備いただくことができます。 手元供養品を生前に準備しても大丈夫? 手元供養品を生前に準備することを、“なんとなく縁起が悪いような気がして…”とためらわれる方もいらっしゃいます。同じように生前にお墓を建てたり、お仏壇を購入されたりする際にも、縁起が悪いと言われることは少なくないようです。 しかし実は、これらはとくに根拠のない迷信で、まったく気にされる必要はありません。むしろ、生前にお墓を建てることは「寿陵(じゅりょう)」、お仏壇を買うことは「寿院(じゅいん)」とそれぞれ呼ばれ、とても縁起の良いこととされているのです。 こうしたことから、手元供養品も生前に準備することには何も問題ないと言って間違いないでしょう。 また現実的な側面においても、生前からご自分でその行く末について事前に決めておかれることは、ご自身とご家族の安心を得られるというメリットがあります。誰しもいつかは必ず迎えるその日のために、ご家族と一緒に様々な準備について考えてみられてはいかがでしょうか。 おわりに 大切な人を亡くした深い悲しみの中で。 あるいはやがて訪れる別れの日を考えて。 手元供養の準備をされる方のご事情や、想いは人それぞれです。手元供養品などの準備についてお困りのことやご質問などは、ぜひお気軽に未来創想へお問い合わせください。お一人お一人のお声に耳を傾け、よりご満足いただけるよう、様々なご提案をさせていただきます。










