その他記事

形見分けとは?マナーや注意点を解説!生前から準備してトラブルを避けよう
故人の大切な品を遺族や親しい人へ分ける「形見分け」は、思い出とともに気持ちをつなぐ大切な供養のひとつです。 本記事では、形見分けの意味やマナー、時期、注意点までをわかりやすく解説します。形見分けの品物としておすすめの遺骨アクセサリーも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。 形見分けとは? 形見分けとは、故人が生前に使用していた品を、親族や親しかった方々へ分け渡すことで、思い出を共有し、故人を偲ぶ供養の一つです。大切な人の持ち物を受け継ぐことで、遺された人々の心の支えにもなります。 この風習の起源は、仏教の祖・お釈迦様が亡くなった際、弟子たちに遺品を分け与えたという逸話にあると伝えられています。また、「身に着けていた品には魂が宿る」という考え方から、形見分けの文化が根付き、現代にも受け継がれているのです。 一般的に、故人より目上の方に形見を贈るのは控えるのがマナーとされていますが、故人の意志や生前の約束がある場合は、失礼にはあたりません。状況に応じて丁寧に対応することが大切です。 形見分けと遺品整理の違いは? 形見分けと遺品整理の違いは、目的と対象にあります。形見分けは、故人が特に大切にしていた品を、血縁者や親しかった人へ贈り、思い出を共有しながら故人を偲ぶ行為です。 一方の遺品整理は、故人が生前使っていたすべての品を整理し、住まいを整える作業であり、思い入れの有無に関わらず日用品や家具なども含まれます。多くの場合、遺品整理の中で形見にふさわしい品を選び、それを形見分けに使う流れとなります。 形見分けと遺産分割の違いは? 遺産分割は、金銭や不動産など財産的価値のあるものを、相続人で話し合って分ける手続きです。 一方、形見分けは原則として、金銭的価値が高くない思い出の品が対象です。ただし、高額な品を形見として扱う場合は、相続財産と見なされ、遺産分割の対象になる可能性があるため注意が必要です。 形見分けに適した品物と適さない品物 形見として適している品物には、故人が生前に愛用していたり、大切に扱っていた物が選ばれることが一般的です。 たとえば、指輪やネックレス、ブローチといったアクセサリーのほか、メガネや万年筆などの小物類、着物やスーツなどの衣類もよく選ばれます。また、絵画・骨董品・レコード・古書など、故人の趣味に関するコレクション類も、思い出を共有する形見として適しています。 家具や家電も、状態がよければ形見の品として贈ることができます。一方、破損していたり故障して使えない品物や、用途がわからないものは形見としては不向きです。また、現金や金券などは形見ではなく「相続財産」として扱われるため、配慮が必要です。 さらに、生き物を形見として贈る場合は、相手の了承を得てから渡すことが大切です。形見は想いを託す品ですから、贈る相手への配慮を忘れずに選びましょう。 形見分けを行う時期を宗教別で解説 形見分けを行う明確な時期に決まりはありませんが、宗教や地域の風習によって目安となるタイミングがあります。 ここでは仏教・神道・キリスト教それぞれの考え方に基づき、一般的な形見分けの時期についてわかりやすく解説します。 仏教の場合 仏教においては、形見分けは一般的に「忌明け」となる四十九日法要を終えたタイミングで行われます。これは、故人が亡くなった後、初七日から七日ごとに計七回の審判を受け、四十九日目に来世の行き先が決まるという考えに基づいています。 遺族はこの期間、故人が極楽浄土へと導かれるよう供養を続け、四十九日法要で一区切りを迎えます。その後、日常生活に戻る節目として形見分けを行うのが習わしです。 ただし、地域やご家族の考え方によっては、五七日(35日目)を忌明けとして形見分けを行うこともあります。 キリスト教の場合 キリスト教では、カトリックとプロテスタントで追悼の流れが異なります。カトリックでは、亡くなった日から数えて3日目、7日目、30日目に追悼ミサが行われ、プロテスタントでは通常、1ヵ月後に召天記念式が執り行われます。 もともとキリスト教には「形見分け」という習慣はありませんが、日本においては30日を一つの区切りとして、追悼ミサや記念式が終わった後に形見分けを行うことが一般的になっています。宗教的な意味合いよりも、故人を偲ぶ気持ちを共有する場として受け入れられています。 神道の場合 神道では、故人の魂はやがて家や家族を見守る守護神となると考えられており、その過程で「霊祭」と呼ばれる儀式が行われます。葬儀後、10日ごとに霊祭を重ね、五十日祭で正式に守護神として迎えられると同時に忌明けを迎えます。 この五十日祭の時期が、形見分けを行う一般的なタイミングとされています。ただし、宗派や地域の慣習によっては、三十日祭で形見分けを行うこともあります。いずれにしても、故人への敬意と遺族の気持ちに配慮しながら、適切な時期を選ぶことが大切です。...
形見分けとは?マナーや注意点を解説!生前から準備してトラブルを避けよう
故人の大切な品を遺族や親しい人へ分ける「形見分け」は、思い出とともに気持ちをつなぐ大切な供養のひとつです。 本記事では、形見分けの意味やマナー、時期、注意点までをわかりやすく解説します。形見分けの品物としておすすめの遺骨アクセサリーも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。 形見分けとは? 形見分けとは、故人が生前に使用していた品を、親族や親しかった方々へ分け渡すことで、思い出を共有し、故人を偲ぶ供養の一つです。大切な人の持ち物を受け継ぐことで、遺された人々の心の支えにもなります。 この風習の起源は、仏教の祖・お釈迦様が亡くなった際、弟子たちに遺品を分け与えたという逸話にあると伝えられています。また、「身に着けていた品には魂が宿る」という考え方から、形見分けの文化が根付き、現代にも受け継がれているのです。 一般的に、故人より目上の方に形見を贈るのは控えるのがマナーとされていますが、故人の意志や生前の約束がある場合は、失礼にはあたりません。状況に応じて丁寧に対応することが大切です。 形見分けと遺品整理の違いは? 形見分けと遺品整理の違いは、目的と対象にあります。形見分けは、故人が特に大切にしていた品を、血縁者や親しかった人へ贈り、思い出を共有しながら故人を偲ぶ行為です。 一方の遺品整理は、故人が生前使っていたすべての品を整理し、住まいを整える作業であり、思い入れの有無に関わらず日用品や家具なども含まれます。多くの場合、遺品整理の中で形見にふさわしい品を選び、それを形見分けに使う流れとなります。 形見分けと遺産分割の違いは? 遺産分割は、金銭や不動産など財産的価値のあるものを、相続人で話し合って分ける手続きです。 一方、形見分けは原則として、金銭的価値が高くない思い出の品が対象です。ただし、高額な品を形見として扱う場合は、相続財産と見なされ、遺産分割の対象になる可能性があるため注意が必要です。 形見分けに適した品物と適さない品物 形見として適している品物には、故人が生前に愛用していたり、大切に扱っていた物が選ばれることが一般的です。 たとえば、指輪やネックレス、ブローチといったアクセサリーのほか、メガネや万年筆などの小物類、着物やスーツなどの衣類もよく選ばれます。また、絵画・骨董品・レコード・古書など、故人の趣味に関するコレクション類も、思い出を共有する形見として適しています。 家具や家電も、状態がよければ形見の品として贈ることができます。一方、破損していたり故障して使えない品物や、用途がわからないものは形見としては不向きです。また、現金や金券などは形見ではなく「相続財産」として扱われるため、配慮が必要です。 さらに、生き物を形見として贈る場合は、相手の了承を得てから渡すことが大切です。形見は想いを託す品ですから、贈る相手への配慮を忘れずに選びましょう。 形見分けを行う時期を宗教別で解説 形見分けを行う明確な時期に決まりはありませんが、宗教や地域の風習によって目安となるタイミングがあります。 ここでは仏教・神道・キリスト教それぞれの考え方に基づき、一般的な形見分けの時期についてわかりやすく解説します。 仏教の場合 仏教においては、形見分けは一般的に「忌明け」となる四十九日法要を終えたタイミングで行われます。これは、故人が亡くなった後、初七日から七日ごとに計七回の審判を受け、四十九日目に来世の行き先が決まるという考えに基づいています。 遺族はこの期間、故人が極楽浄土へと導かれるよう供養を続け、四十九日法要で一区切りを迎えます。その後、日常生活に戻る節目として形見分けを行うのが習わしです。 ただし、地域やご家族の考え方によっては、五七日(35日目)を忌明けとして形見分けを行うこともあります。 キリスト教の場合 キリスト教では、カトリックとプロテスタントで追悼の流れが異なります。カトリックでは、亡くなった日から数えて3日目、7日目、30日目に追悼ミサが行われ、プロテスタントでは通常、1ヵ月後に召天記念式が執り行われます。 もともとキリスト教には「形見分け」という習慣はありませんが、日本においては30日を一つの区切りとして、追悼ミサや記念式が終わった後に形見分けを行うことが一般的になっています。宗教的な意味合いよりも、故人を偲ぶ気持ちを共有する場として受け入れられています。 神道の場合 神道では、故人の魂はやがて家や家族を見守る守護神となると考えられており、その過程で「霊祭」と呼ばれる儀式が行われます。葬儀後、10日ごとに霊祭を重ね、五十日祭で正式に守護神として迎えられると同時に忌明けを迎えます。 この五十日祭の時期が、形見分けを行う一般的なタイミングとされています。ただし、宗派や地域の慣習によっては、三十日祭で形見分けを行うこともあります。いずれにしても、故人への敬意と遺族の気持ちに配慮しながら、適切な時期を選ぶことが大切です。...

預骨とは?利用できるケースや御礼・預骨の注意点まで詳しく解説
預骨(よこつ)とは、一時的に遺骨を預けることをいいます。預け先は、お寺、葬祭会館、 預骨堂などがあります。以前は、身内が亡くなると葬儀を行い、遺骨は遺族のもとで保管し、適切なタイミングで納骨をしていました。 しかし、近年はさまざまな事情があり、納骨までの間に一時的に預骨を選ぶケースも増えています。本記事では、預骨できる場所や費用相場、預けられる期間などについて詳しく解説していきます。また、預骨ではなく、長期保管の方法として人気のある手元供養についても紹介するので参考にしてください。 預骨とは 預骨は、「よこつ」と読みます。葬儀を終えた遺骨を一時的に預けることをいいます。一般的には身内が亡くなった場合、遺骨は遺族が納骨まで保管することが多いです。しかし、近年は「お墓が遠方にあってなかなか納骨に行けない」「お墓がまだ用意できていないので納骨できない」など、さまざまな理由で一時的に遺骨を専門施設に預ける方も少なくありません。 預骨は、受け入れてくれる施設と契約し、期間を決めて遺骨を預かってもらうサービスです。申込書を記入したり保管料を支払ったりして一定の期間遺骨を保管してもらいます。 預骨と納骨の違い 「遺骨を預かってもらうということは、預骨は納骨と同じではないか」と思う方もいるかもしれません。しかし、預骨と納骨とは異なります。納骨堂に遺骨を納骨する場合、納骨堂のスペースを使用する権利を購入するか、使用料を支払わなければいけません。 預骨の場合は、一時的に遺骨を預かってもらうため、決められた期間の間だけ遺骨を保管してもらいます。預骨の契約期間が終わった後は、引き取るかお墓や納骨堂に納骨するなど、最終的な故人の供養方法を用意する必要があります。 つまり、預骨とは遺骨の最終的な供養方法がまだ決まっていない方のための、一時的な預け場所なのです。 預骨を利用するシーン 預骨を利用する理由は、さまざまあります。 お墓がなく、お墓を作る準備に時間がかかる 遠方にお墓があり、納骨するまで時間がある 遺骨をすぐに引き取ることができない 急に身内が亡くなり、気持ちの整理がまだできていない 宗教的にも安心して供養できる場所を探したい 家族の間で、納骨する場所に関して意見がまとまらない 墓じまいすることになった お墓がない場合や、お墓があっても遠方で納骨までの期間がある場合、預骨を選ぶ方は少なくありません。また、家族が海外に住んでいてすぐに遺骨を引き取れないケースもあるでしょう。 納骨する場所に関して、家族で意見を統一するまで預骨を利用する方もいます。また、一旦、お墓に納骨してあっても事情があり墓じまいすることになり、遺骨を預けることもあります。 預骨ができる場所 預骨ができる場所は、以下のようなところです。 寺院などの宗教法人 葬儀社 民営の霊園 納骨堂 石材店 散骨・墓じまいのなどを行う専門業者 通常、納骨を受け付けている施設であれば、基本的に預骨にも応じてくれると考えてよいでしょう。また、公式サイトやパンフレットなどに預骨を行っていると明記されていない施設でも、直接話せば受け入れてくれる場合があるので確認してみましょう。...
預骨とは?利用できるケースや御礼・預骨の注意点まで詳しく解説
預骨(よこつ)とは、一時的に遺骨を預けることをいいます。預け先は、お寺、葬祭会館、 預骨堂などがあります。以前は、身内が亡くなると葬儀を行い、遺骨は遺族のもとで保管し、適切なタイミングで納骨をしていました。 しかし、近年はさまざまな事情があり、納骨までの間に一時的に預骨を選ぶケースも増えています。本記事では、預骨できる場所や費用相場、預けられる期間などについて詳しく解説していきます。また、預骨ではなく、長期保管の方法として人気のある手元供養についても紹介するので参考にしてください。 預骨とは 預骨は、「よこつ」と読みます。葬儀を終えた遺骨を一時的に預けることをいいます。一般的には身内が亡くなった場合、遺骨は遺族が納骨まで保管することが多いです。しかし、近年は「お墓が遠方にあってなかなか納骨に行けない」「お墓がまだ用意できていないので納骨できない」など、さまざまな理由で一時的に遺骨を専門施設に預ける方も少なくありません。 預骨は、受け入れてくれる施設と契約し、期間を決めて遺骨を預かってもらうサービスです。申込書を記入したり保管料を支払ったりして一定の期間遺骨を保管してもらいます。 預骨と納骨の違い 「遺骨を預かってもらうということは、預骨は納骨と同じではないか」と思う方もいるかもしれません。しかし、預骨と納骨とは異なります。納骨堂に遺骨を納骨する場合、納骨堂のスペースを使用する権利を購入するか、使用料を支払わなければいけません。 預骨の場合は、一時的に遺骨を預かってもらうため、決められた期間の間だけ遺骨を保管してもらいます。預骨の契約期間が終わった後は、引き取るかお墓や納骨堂に納骨するなど、最終的な故人の供養方法を用意する必要があります。 つまり、預骨とは遺骨の最終的な供養方法がまだ決まっていない方のための、一時的な預け場所なのです。 預骨を利用するシーン 預骨を利用する理由は、さまざまあります。 お墓がなく、お墓を作る準備に時間がかかる 遠方にお墓があり、納骨するまで時間がある 遺骨をすぐに引き取ることができない 急に身内が亡くなり、気持ちの整理がまだできていない 宗教的にも安心して供養できる場所を探したい 家族の間で、納骨する場所に関して意見がまとまらない 墓じまいすることになった お墓がない場合や、お墓があっても遠方で納骨までの期間がある場合、預骨を選ぶ方は少なくありません。また、家族が海外に住んでいてすぐに遺骨を引き取れないケースもあるでしょう。 納骨する場所に関して、家族で意見を統一するまで預骨を利用する方もいます。また、一旦、お墓に納骨してあっても事情があり墓じまいすることになり、遺骨を預けることもあります。 預骨ができる場所 預骨ができる場所は、以下のようなところです。 寺院などの宗教法人 葬儀社 民営の霊園 納骨堂 石材店 散骨・墓じまいのなどを行う専門業者 通常、納骨を受け付けている施設であれば、基本的に預骨にも応じてくれると考えてよいでしょう。また、公式サイトやパンフレットなどに預骨を行っていると明記されていない施設でも、直接話せば受け入れてくれる場合があるので確認してみましょう。...

お寺や納骨堂で遺骨の一時預かりはできる?費用や期間などを詳しく解説
お寺や納骨堂、霊園では、一定期間遺骨を預かるサービスを提供しています。 遺骨は、自宅で保管することも可能ですが、管理の手間や環境面の影響を考えると、専門施設の利用が安心です。本記事では、遺骨の一時預かりのメリットや注意点、費用相場について詳しく解説します。 遺骨の一時預かりとは? 遺骨の一時預かりとは、一定期間、お寺や専門施設に遺骨を預けて保管してもらうことを指し、「預骨」と呼ばれることもあります。お墓や供養方法が決まっていない場合や、経済的な理由ですぐにお墓を用意できないこともあります。 また、遺骨を自宅に安置することも可能ですが、「住宅が狭くて置く場所がない」「家族の意見がまとまらない」といった理由で、自宅保管が難しいケースも少なくありません。 こうした状況の際に、遺骨の一時預かりを利用すれば、落ち着いてお墓の準備を進めたり、家族で今後の供養方法についてじっくり話し合う時間を確保することができます。 遺骨の一時預かりを利用するメリット 遺骨の一時預かりを利用する最大のメリットは、納骨方法をじっくり検討し、準備する時間的な余裕が得られることです。突然の訃報によりお墓の準備が間に合わない場合でも、遺骨を一時的に預けることで、家族と相談しながら今後の方針を決めることができます。 また、建墓や永代供養に比べて費用を抑えられるため、すぐにお墓を用意できない場合でも、預かり期間中に資金を準備することが可能です。さらに、専門施設での保管により、湿度や温度管理が徹底され、カビの発生や骨壺の破損といったリスクを避けられます。 自宅での保管に不安がある場合でも、安全な環境で適切に管理してもらえるため、安心して預けることができるのが大きなメリットです。 遺骨の一時預かりを利用するデメリット 遺骨の一時預かりは預かり期間が短く設定されているため、長期間の利用には向いていません。 多くの施設では1~2年が一般的で、延長できる場合もありますが、回数に制限があることが多く、最終的には納骨先を決める必要があります。また、利用期間が限られているため、預けたことで安心してしまい、納骨先の決定が先延ばしになりがちです。 さらに、預かり期間を延長する際には更新手続きが必要になり、施設によっては直接出向く必要があるため、遠方に住んでいる場合は負担になることもあります。 短期間の保管を前提としたサービスであるため、最終的な供養の方法を早めに決めることが重要です。 お寺の納骨堂での一時預かりと永代供養の違い 遺骨の一時預かりは、納骨先が未定の場合やお墓の準備が整うまでの間、一定期間施設に遺骨を保管してもらうサービスです。通常は数ヶ月から数年の期間で、更新が可能な場合もありますが、長期間の預かりには追加費用がかかることがあります。 一方、永代供養は、遺族に代わって寺院や霊園が遺骨を永久的に管理し、定期的に供養を行うものです。初期費用はかかるものの、その後の維持費は不要な場合が多く、後継者がいない方に適しています。 一時預かりは将来的に遺骨を移動させることが前提ですが、永代供養は最終的な安置方法として選ばれることが一般的です。 遺骨の一時預かりを行う施設と費用相場 遺骨の一時預かりを実施している施設には、お寺や宗教法人、民営霊園、公営墓地、葬儀社、石材店 などがあります。一般的に、納骨を受け入れている施設であれば、一時預かりにも対応していることが多いですが、公に案内していない場合もあるため、希望する施設があれば事前に問い合わせて確認することが重要です。 また、公営墓地の中には、遺骨を一時的に収蔵できる施設を併設している場合もあります。利用には制限があることもあるため、自治体や墓地の管理事務所に相談し、対応可能な施設を紹介してもらうとスムーズです。 一時預かりの料金は施設によって異なり、以下が一般的な相場となります。 施設の種類 年間料金相場 民営霊園 1~3万円 公営霊園...
お寺や納骨堂で遺骨の一時預かりはできる?費用や期間などを詳しく解説
お寺や納骨堂、霊園では、一定期間遺骨を預かるサービスを提供しています。 遺骨は、自宅で保管することも可能ですが、管理の手間や環境面の影響を考えると、専門施設の利用が安心です。本記事では、遺骨の一時預かりのメリットや注意点、費用相場について詳しく解説します。 遺骨の一時預かりとは? 遺骨の一時預かりとは、一定期間、お寺や専門施設に遺骨を預けて保管してもらうことを指し、「預骨」と呼ばれることもあります。お墓や供養方法が決まっていない場合や、経済的な理由ですぐにお墓を用意できないこともあります。 また、遺骨を自宅に安置することも可能ですが、「住宅が狭くて置く場所がない」「家族の意見がまとまらない」といった理由で、自宅保管が難しいケースも少なくありません。 こうした状況の際に、遺骨の一時預かりを利用すれば、落ち着いてお墓の準備を進めたり、家族で今後の供養方法についてじっくり話し合う時間を確保することができます。 遺骨の一時預かりを利用するメリット 遺骨の一時預かりを利用する最大のメリットは、納骨方法をじっくり検討し、準備する時間的な余裕が得られることです。突然の訃報によりお墓の準備が間に合わない場合でも、遺骨を一時的に預けることで、家族と相談しながら今後の方針を決めることができます。 また、建墓や永代供養に比べて費用を抑えられるため、すぐにお墓を用意できない場合でも、預かり期間中に資金を準備することが可能です。さらに、専門施設での保管により、湿度や温度管理が徹底され、カビの発生や骨壺の破損といったリスクを避けられます。 自宅での保管に不安がある場合でも、安全な環境で適切に管理してもらえるため、安心して預けることができるのが大きなメリットです。 遺骨の一時預かりを利用するデメリット 遺骨の一時預かりは預かり期間が短く設定されているため、長期間の利用には向いていません。 多くの施設では1~2年が一般的で、延長できる場合もありますが、回数に制限があることが多く、最終的には納骨先を決める必要があります。また、利用期間が限られているため、預けたことで安心してしまい、納骨先の決定が先延ばしになりがちです。 さらに、預かり期間を延長する際には更新手続きが必要になり、施設によっては直接出向く必要があるため、遠方に住んでいる場合は負担になることもあります。 短期間の保管を前提としたサービスであるため、最終的な供養の方法を早めに決めることが重要です。 お寺の納骨堂での一時預かりと永代供養の違い 遺骨の一時預かりは、納骨先が未定の場合やお墓の準備が整うまでの間、一定期間施設に遺骨を保管してもらうサービスです。通常は数ヶ月から数年の期間で、更新が可能な場合もありますが、長期間の預かりには追加費用がかかることがあります。 一方、永代供養は、遺族に代わって寺院や霊園が遺骨を永久的に管理し、定期的に供養を行うものです。初期費用はかかるものの、その後の維持費は不要な場合が多く、後継者がいない方に適しています。 一時預かりは将来的に遺骨を移動させることが前提ですが、永代供養は最終的な安置方法として選ばれることが一般的です。 遺骨の一時預かりを行う施設と費用相場 遺骨の一時預かりを実施している施設には、お寺や宗教法人、民営霊園、公営墓地、葬儀社、石材店 などがあります。一般的に、納骨を受け入れている施設であれば、一時預かりにも対応していることが多いですが、公に案内していない場合もあるため、希望する施設があれば事前に問い合わせて確認することが重要です。 また、公営墓地の中には、遺骨を一時的に収蔵できる施設を併設している場合もあります。利用には制限があることもあるため、自治体や墓地の管理事務所に相談し、対応可能な施設を紹介してもらうとスムーズです。 一時預かりの料金は施設によって異なり、以下が一般的な相場となります。 施設の種類 年間料金相場 民営霊園 1~3万円 公営霊園...

遺骨の一時預かりとは|永代供養との違いや期間なども詳しく解説
遺骨の一時預かりとは、身内や親戚などの遺骨を一時的に別の場所で保管してもらうことです。一般的には人が亡くなると葬儀を行い、納骨先を決めますが、さまざまな事情ですぐには決まらないこともあるため、そのような際に遺骨の一時預かりは便利です。 しかし、預骨とも呼ばれる一時預かりには、預けられる場所や期間、条件などが決まっているため、それに従って一定期間だけ遺骨を預けなければいけません。 本記事では、遺骨の一時預かりの仕組みや、メリット・デメリットについて詳しく解説します。また、自宅保管する際のおすすめのグッズなども紹介しているので、あわせてごらんください。 遺骨の一時預かりとは 遺骨の一時預かりとは、寺院や葬儀社、納骨堂などの専門施設に遺骨を一時的に保管することです。遺骨を別の場所に預けることから、預骨と呼ばれることもあります。 一般的には、人が亡くなると各宗派の作法に従って葬儀を執り行い、納骨されますが、身内が突然亡くなったり、親族間でお墓や納骨についての話し合いがまとまらなかったりする場合などは、納骨先がすぐに決まらないことも少なくありません。 納骨先が決まるまでの間、遺骨の一時預かりを利用することは、費用を安く抑えながら、ゆっくり親族で話し合いの時間を持つことができる方法といえます。 遺骨を一時預かりしてくれる場所 遺骨を預かってくれる場所は決まっています。主に、寺院などの宗教法人、民営の霊園、葬儀社、納骨堂、石材店などです。納骨を受け付けている施設であれば、基本的に遺骨の一時預かりもしてくれると考えてよいでしょう。 また、公式サイトやパンフレットなどに遺骨の一時預かりが明記されていない施設でも受け入れてくれる場合があるので、事前に確認してみましょう。 遺骨の一時預かりを依頼する条件 遺骨の一時預かりを利用する場合、一定の条件があります。条件は施設によって異なるため、預ける前にそれぞれの施設に問い合わせておきましょう。一般的な遺骨の一時預かりの条件は、次のようなものです。 亡くなってから納骨、埋葬されていない遺骨である 火葬許可証を持っている 故人の親族によって遺骨の一時預かりを申し込んでいる 施設のある地域内に住所がある 遺骨は預ける方の住所が、施設のある地域内でなければいけません。遺骨の一時預かりをしてくれる場所を探す際には、近くの施設から探してみるとよいでしょう。 遺骨を一時預かりしてくれる期間 遺骨の一時預かりの期間は、預け入れる先によって異なります。1~2年というところもあれば、長くて6年まで受け入れてくれるところもあるため、納骨までの準備に時間がかかりそうな場合は、長く預かってくれるところを探した方がよいでしょう。 あくまでも、遺骨の一時預かりは、遺骨の安置場所やお墓を用意したりするまでの一時的な保管先です。 遺骨の一時預かりの費用相場 遺骨の一時預かりの費用相場は、次の通りです。 施設 料金相場(年間) 公営霊園 3,000~6,000円程度 民営霊園 12,000~24,000円程度 寺院、宗教法人 30,000~50,000円程度...
遺骨の一時預かりとは|永代供養との違いや期間なども詳しく解説
遺骨の一時預かりとは、身内や親戚などの遺骨を一時的に別の場所で保管してもらうことです。一般的には人が亡くなると葬儀を行い、納骨先を決めますが、さまざまな事情ですぐには決まらないこともあるため、そのような際に遺骨の一時預かりは便利です。 しかし、預骨とも呼ばれる一時預かりには、預けられる場所や期間、条件などが決まっているため、それに従って一定期間だけ遺骨を預けなければいけません。 本記事では、遺骨の一時預かりの仕組みや、メリット・デメリットについて詳しく解説します。また、自宅保管する際のおすすめのグッズなども紹介しているので、あわせてごらんください。 遺骨の一時預かりとは 遺骨の一時預かりとは、寺院や葬儀社、納骨堂などの専門施設に遺骨を一時的に保管することです。遺骨を別の場所に預けることから、預骨と呼ばれることもあります。 一般的には、人が亡くなると各宗派の作法に従って葬儀を執り行い、納骨されますが、身内が突然亡くなったり、親族間でお墓や納骨についての話し合いがまとまらなかったりする場合などは、納骨先がすぐに決まらないことも少なくありません。 納骨先が決まるまでの間、遺骨の一時預かりを利用することは、費用を安く抑えながら、ゆっくり親族で話し合いの時間を持つことができる方法といえます。 遺骨を一時預かりしてくれる場所 遺骨を預かってくれる場所は決まっています。主に、寺院などの宗教法人、民営の霊園、葬儀社、納骨堂、石材店などです。納骨を受け付けている施設であれば、基本的に遺骨の一時預かりもしてくれると考えてよいでしょう。 また、公式サイトやパンフレットなどに遺骨の一時預かりが明記されていない施設でも受け入れてくれる場合があるので、事前に確認してみましょう。 遺骨の一時預かりを依頼する条件 遺骨の一時預かりを利用する場合、一定の条件があります。条件は施設によって異なるため、預ける前にそれぞれの施設に問い合わせておきましょう。一般的な遺骨の一時預かりの条件は、次のようなものです。 亡くなってから納骨、埋葬されていない遺骨である 火葬許可証を持っている 故人の親族によって遺骨の一時預かりを申し込んでいる 施設のある地域内に住所がある 遺骨は預ける方の住所が、施設のある地域内でなければいけません。遺骨の一時預かりをしてくれる場所を探す際には、近くの施設から探してみるとよいでしょう。 遺骨を一時預かりしてくれる期間 遺骨の一時預かりの期間は、預け入れる先によって異なります。1~2年というところもあれば、長くて6年まで受け入れてくれるところもあるため、納骨までの準備に時間がかかりそうな場合は、長く預かってくれるところを探した方がよいでしょう。 あくまでも、遺骨の一時預かりは、遺骨の安置場所やお墓を用意したりするまでの一時的な保管先です。 遺骨の一時預かりの費用相場 遺骨の一時預かりの費用相場は、次の通りです。 施設 料金相場(年間) 公営霊園 3,000~6,000円程度 民営霊園 12,000~24,000円程度 寺院、宗教法人 30,000~50,000円程度...

葬儀費用の相場はいくらぐらい?内訳や注意点・費用を抑えるポイントを解説
葬儀にかかる費用については、相場が分からず不安に思う方も多いことでしょう。 ここでは、葬儀の費用に関する内訳や注意点について詳しく解説しながら、費用を抑えるポイントなども紹介していきます。 葬儀費用の平均はいくらぐらい? あくまでも大まかな目安となりますが、葬儀費用の全国平均は195万円ほどといわれています。 これは、葬儀費用に飲食・接待費用や宗教者へのお礼を含んだ平均費用ですが、葬儀の規模や内容・地域によってもかなりバラつきがありますので、相場はおおよそ200万円前後と心得ておくとよいでしょう。 葬儀費用をさらに掘り下げて、内訳別の平均費用についても解説します。 葬儀費用の内訳とそれぞれの平均費用 先にも触れましたが、葬儀費用の内訳は大きく、葬儀一式にかかる費用・飲食接待にかかる費用・宗教者にかかる費用の3つに分かれます。 葬儀費用全国平均の195万円を例に、それぞれにかかる平均費用を解説します。 葬儀一式にかかる費用 【平均費用:120万円】 葬儀一式料金はおよそ120万円と、葬儀費用全体で一番多くの割合を占めます。料金には一般的に、 ご遺体の移送・安置費用 霊柩車・タクシー・マイクロバスなどの車両費用 会場費 祭壇・棺・受付用品などにかかる費用 司会進行費用 死亡届や火葬場利用手続きの代行費用 火葬費用 などが含まれています。 飲食接待にかかる費用 【平均費用:30万円】 通夜振る舞い・精進落としなど、葬儀や通夜式の際に振る舞う飲食費用です。 日本の風習では、通夜の参列者に食事等を振る舞う「通夜振る舞い」が、故人の供養になるといわれています。 食事については、料理の内容や、葬儀社に手配を頼むか・自分で準備をするかによっても、費用が前後します。 宗教者にかかる費用(仏式) 【平均費用:45万円】 読経や戒名料などのお布施や、僧侶のお車代などの費用です。 戒名のランクや住んでいる地域によっても、宗教者にかかる費用は前後します。 葬儀形式別の費用相場...
葬儀費用の相場はいくらぐらい?内訳や注意点・費用を抑えるポイントを解説
葬儀にかかる費用については、相場が分からず不安に思う方も多いことでしょう。 ここでは、葬儀の費用に関する内訳や注意点について詳しく解説しながら、費用を抑えるポイントなども紹介していきます。 葬儀費用の平均はいくらぐらい? あくまでも大まかな目安となりますが、葬儀費用の全国平均は195万円ほどといわれています。 これは、葬儀費用に飲食・接待費用や宗教者へのお礼を含んだ平均費用ですが、葬儀の規模や内容・地域によってもかなりバラつきがありますので、相場はおおよそ200万円前後と心得ておくとよいでしょう。 葬儀費用をさらに掘り下げて、内訳別の平均費用についても解説します。 葬儀費用の内訳とそれぞれの平均費用 先にも触れましたが、葬儀費用の内訳は大きく、葬儀一式にかかる費用・飲食接待にかかる費用・宗教者にかかる費用の3つに分かれます。 葬儀費用全国平均の195万円を例に、それぞれにかかる平均費用を解説します。 葬儀一式にかかる費用 【平均費用:120万円】 葬儀一式料金はおよそ120万円と、葬儀費用全体で一番多くの割合を占めます。料金には一般的に、 ご遺体の移送・安置費用 霊柩車・タクシー・マイクロバスなどの車両費用 会場費 祭壇・棺・受付用品などにかかる費用 司会進行費用 死亡届や火葬場利用手続きの代行費用 火葬費用 などが含まれています。 飲食接待にかかる費用 【平均費用:30万円】 通夜振る舞い・精進落としなど、葬儀や通夜式の際に振る舞う飲食費用です。 日本の風習では、通夜の参列者に食事等を振る舞う「通夜振る舞い」が、故人の供養になるといわれています。 食事については、料理の内容や、葬儀社に手配を頼むか・自分で準備をするかによっても、費用が前後します。 宗教者にかかる費用(仏式) 【平均費用:45万円】 読経や戒名料などのお布施や、僧侶のお車代などの費用です。 戒名のランクや住んでいる地域によっても、宗教者にかかる費用は前後します。 葬儀形式別の費用相場...
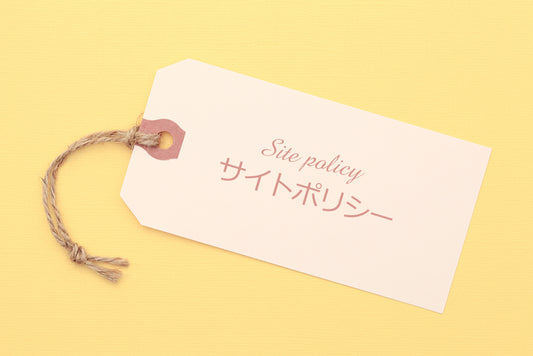
サイトポリシー
サイトポリシー 免責事項、各コンテンツの著作権や個人情報の取り扱いなど、当サイトを皆様が安心してご利用いただけるための各種情報の取り扱いに関するポリシーは以下の通りです。 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」のご利用にあたっては、以下をお読みいただき、これらの事項をご確認、ご同意の上でご利用ください。 免責について 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」におけるコンテンツの信頼性を確保するよう努力をしますが、「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」に掲載されたコンテンツ内容に誤謬・正確性や遅延などについて、(株)未来創想およびその情報提供者は一切の責任を負いません。 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」に掲載されている情報に基づいて被ったとされる損害について、(株)未来創想およびその情報提供者は一切の責任を負いません。 (株)未来創想は、システムの保守、電気通信事業者、データセンターの障害、天災などが生じた場合、「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」のサービスを停止することがあります。その際、(株)未来創想は「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」のサービス停止によって利用者が被った損害について、一切の責任を負いません。 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」から外部サイトにリンクしている場合、その内容の信頼性などについて(株)未来創想およびその情報提供者は一切の責任を負いません。 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」に記載されている事項は予告なしに変更されることがあります。 著作権について 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」のコンテンツの著作権は、(株)未来創想またはその著作者に帰属します。 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」のコンテンツを、著作権者の承諾なしに改編、複製、転載、変更、翻案、再配布することを禁じます。 リンクについて 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」へのリンクはお断りしております。 URLは予告なく変更・削除することがあります。 サイトポリシーの変更 (株)未来創想は、お客様に事前の通知を行うことなく本サイトポリシーを変更することがあります。当該変更は本サイトポリシー掲載ページに、変更された本サイトポリシーが掲載されることをもって有効とします。 お客様は、変更された本サイトポリシーが有効となった後、当ウェブサイトを使用することにより、当該変更を承諾したものとみなします。
サイトポリシー
サイトポリシー 免責事項、各コンテンツの著作権や個人情報の取り扱いなど、当サイトを皆様が安心してご利用いただけるための各種情報の取り扱いに関するポリシーは以下の通りです。 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」のご利用にあたっては、以下をお読みいただき、これらの事項をご確認、ご同意の上でご利用ください。 免責について 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」におけるコンテンツの信頼性を確保するよう努力をしますが、「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」に掲載されたコンテンツ内容に誤謬・正確性や遅延などについて、(株)未来創想およびその情報提供者は一切の責任を負いません。 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」に掲載されている情報に基づいて被ったとされる損害について、(株)未来創想およびその情報提供者は一切の責任を負いません。 (株)未来創想は、システムの保守、電気通信事業者、データセンターの障害、天災などが生じた場合、「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」のサービスを停止することがあります。その際、(株)未来創想は「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」のサービス停止によって利用者が被った損害について、一切の責任を負いません。 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」から外部サイトにリンクしている場合、その内容の信頼性などについて(株)未来創想およびその情報提供者は一切の責任を負いません。 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」に記載されている事項は予告なしに変更されることがあります。 著作権について 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」のコンテンツの著作権は、(株)未来創想またはその著作者に帰属します。 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」のコンテンツを、著作権者の承諾なしに改編、複製、転載、変更、翻案、再配布することを禁じます。 リンクについて 「こんなときどうする?手元供養のお役立ちブログ」へのリンクはお断りしております。 URLは予告なく変更・削除することがあります。 サイトポリシーの変更 (株)未来創想は、お客様に事前の通知を行うことなく本サイトポリシーを変更することがあります。当該変更は本サイトポリシー掲載ページに、変更された本サイトポリシーが掲載されることをもって有効とします。 お客様は、変更された本サイトポリシーが有効となった後、当ウェブサイトを使用することにより、当該変更を承諾したものとみなします。










