その他記事

木のたもとや芝生に、遺骨だけの素朴な自然葬…韓国で増加中
2013年07月19日15時36分 [? 中央日報/中央日報日本語版」 韓国での火葬は「骨あげ」という拾骨を、遺族はおこないません。ご遺骨は斎場の係員により粉骨され、骨壷に入れて遺族に返されます。粉骨された遺灰は、樹木葬などの自然葬に馴染みやすいんでしょうね。 会社員のパク・ソンチョルさん〔54、京畿道南揚州市(キョンギド・ナムヤンジュシ)〕は最近、母親が亡くなるとすぐに遺体を火葬後、樹木葬として弔った。京畿道坡州市竜尾里(パジュシ・ヨンミリ)にあるソウル市立墓地内にある木の周辺に遺体を火葬して埋めたのだ。パクさんは「納骨などほかの葬儀方式に比べて費用が安く、子孫が管理しやすいという点を挙げて家族を説得し樹木葬にした」として「樹木葬は最も自然に親和的な方法」と話した。 火葬が普遍化する中で、自然葬が葬儀文化の一つとして浮上している。自然葬は火葬した遺骨の骨粉を樹木や芝などの下に埋めるものだ。“樹木葬”“芝葬”“草花葬”“海葬”などが代表的な自然葬の形態だ。 韓国保健福祉部などによれば全国の火葬率は2001年の58.9%から2011年には71.1%に増加した。一方、埋葬率は2001年の41.1%から2011年には28.9%と減少した。また自然葬は2009年に3329件、2010年は5269件、2011年には6440件と毎年増加する傾向だ。昨年まで全国に336カ所の自然埋葬地が造成された。 京畿道坡州市竜尾里のソウル市立昇華院の場合、2008年に芝葬を初めて導入したのに続き2011年から樹木葬も運営している。5月末現在の芝葬は一日あたり0.3位、樹木葬は一日あたり5.6位の墓地が造成されている。 国民の自然葬選好度も高まっている様相だ。保健社会研究院の最近の調査によれば自然葬を好む割合は31.2%で納骨施設(25.5%)よりも高い。現在の自然葬が全体の葬儀方式に占める比率は3%と低いが徐々に増加している。 これに伴いソウル市とソウル施設公団は現在8000位を収容できる坡州市竜尾里自然広場を拡大する方針だ。2015年までに5万2000位(3万平方メートル)を安置できるようにするということだ。ここはソウル市民と京畿道坡州・高陽(コヤン)市民らが利用できる。費用は納骨に比べて10分の1と安い上に使用期限が半永久的というところが長所だ。自然葬の費用は1位あたり50万ウォンで使用期間は40年だ。 ソウル市立昇華院のチョ・ソンファ広報担当は「納骨施設は数代にわたる長期的管理が難しく、放置している間に周辺から嫌悪される施設になってしまう可能性もあり、自然葬に対する関心が高まっている傾向」と話した。 韓国政府も先月から家の前庭で自然葬ができるよう許可した。商売などに関する法律施行令を改正して自然埋葬地をつくることができなかった住居・商業・工業地域でも別途の建築物や工作物をつくらず自然埋葬地を設置できるようにしたのだ。福祉部老人支援課のキム・ハクチン担当は「国土を効率的に利用しようとの趣旨で自然葬の活性化政策を展開することになった」と話した。
木のたもとや芝生に、遺骨だけの素朴な自然葬…韓国で増加中
2013年07月19日15時36分 [? 中央日報/中央日報日本語版」 韓国での火葬は「骨あげ」という拾骨を、遺族はおこないません。ご遺骨は斎場の係員により粉骨され、骨壷に入れて遺族に返されます。粉骨された遺灰は、樹木葬などの自然葬に馴染みやすいんでしょうね。 会社員のパク・ソンチョルさん〔54、京畿道南揚州市(キョンギド・ナムヤンジュシ)〕は最近、母親が亡くなるとすぐに遺体を火葬後、樹木葬として弔った。京畿道坡州市竜尾里(パジュシ・ヨンミリ)にあるソウル市立墓地内にある木の周辺に遺体を火葬して埋めたのだ。パクさんは「納骨などほかの葬儀方式に比べて費用が安く、子孫が管理しやすいという点を挙げて家族を説得し樹木葬にした」として「樹木葬は最も自然に親和的な方法」と話した。 火葬が普遍化する中で、自然葬が葬儀文化の一つとして浮上している。自然葬は火葬した遺骨の骨粉を樹木や芝などの下に埋めるものだ。“樹木葬”“芝葬”“草花葬”“海葬”などが代表的な自然葬の形態だ。 韓国保健福祉部などによれば全国の火葬率は2001年の58.9%から2011年には71.1%に増加した。一方、埋葬率は2001年の41.1%から2011年には28.9%と減少した。また自然葬は2009年に3329件、2010年は5269件、2011年には6440件と毎年増加する傾向だ。昨年まで全国に336カ所の自然埋葬地が造成された。 京畿道坡州市竜尾里のソウル市立昇華院の場合、2008年に芝葬を初めて導入したのに続き2011年から樹木葬も運営している。5月末現在の芝葬は一日あたり0.3位、樹木葬は一日あたり5.6位の墓地が造成されている。 国民の自然葬選好度も高まっている様相だ。保健社会研究院の最近の調査によれば自然葬を好む割合は31.2%で納骨施設(25.5%)よりも高い。現在の自然葬が全体の葬儀方式に占める比率は3%と低いが徐々に増加している。 これに伴いソウル市とソウル施設公団は現在8000位を収容できる坡州市竜尾里自然広場を拡大する方針だ。2015年までに5万2000位(3万平方メートル)を安置できるようにするということだ。ここはソウル市民と京畿道坡州・高陽(コヤン)市民らが利用できる。費用は納骨に比べて10分の1と安い上に使用期限が半永久的というところが長所だ。自然葬の費用は1位あたり50万ウォンで使用期間は40年だ。 ソウル市立昇華院のチョ・ソンファ広報担当は「納骨施設は数代にわたる長期的管理が難しく、放置している間に周辺から嫌悪される施設になってしまう可能性もあり、自然葬に対する関心が高まっている傾向」と話した。 韓国政府も先月から家の前庭で自然葬ができるよう許可した。商売などに関する法律施行令を改正して自然埋葬地をつくることができなかった住居・商業・工業地域でも別途の建築物や工作物をつくらず自然埋葬地を設置できるようにしたのだ。福祉部老人支援課のキム・ハクチン担当は「国土を効率的に利用しようとの趣旨で自然葬の活性化政策を展開することになった」と話した。

映画「石巻市立湊小学校避難所」
お向かいの南御堂さんでは、25日〜報恩講というものが催されています。 その一環でしょうか、「南御堂シアター」の第一回として 「石巻市立湊小学校避難所」という映画が放映されました。 無料のイベントですが、事前に申し込みが必要です。 毎日前を通る南御堂の前に宣伝の看板が立てかけられていましたので、 早速申し込んで見ることができました。 まずは、浪江町で語り部をなさっていたという吉川裕子さんが登場。 浪江町で震災当時何度も「ここへ」「あそこへ」と 訳も聞かされないまま避難を強いられたそうです。 今思えば、原発からの放射能が広がって行く方向に逃げたそうで、 「内部被曝はしてるわな」と福島弁でお話されました。 現在は大阪市に住む娘さんの勧めで堺市の公営住宅に避難され、 震災の語り部として活動されているとのことです。 福島から避難してきた人たちは、 家のドアに汚物を下げられるなどの嫌がらせにもあっている、 「早く帰れといわんばかりだ」とも「放射能は伝染りませんから。キスしても大丈夫ですよ」と 冗談を交えて訴える姿も痛ましい思いがしました。 会場では驚きと、非難の声だと思いますが「えええ!」「そんな!」という声が上がりました。 福島弁でユーモアを交えて震災の実際をお話ししている姿に頭が下がります。 また、映画の中ではボランティア団体が歌を歌っている場面で ウサギ追いし・・・「故郷」が流れると 「故郷は故郷がある人がふるさとを思って歌う歌で、 ふるさとがなくなった私たちによく歌うよね!」という厳しい意見も聞かれました。 確かに震災から3〜4ヶ月の段階で「ふるさと」は厳しいですね。 被災者の本音だと思いました。 押し付けのボランティアにならない取り組みが必要だと思いました。 しかし、映画は監督さんの「暗いものにはしたくなかった」というお言葉どおり、 笑いが随所にあり、人々の明るさに驚きます。 4月21日〜10月11日に避難所が閉鎖されるまで、そこに泊まりこみ、 避難者に寄り添いながらカメラを回し続けた監督の思いは確実に伝わってきました。映画『石巻市立湊小学校避難所』...
映画「石巻市立湊小学校避難所」
お向かいの南御堂さんでは、25日〜報恩講というものが催されています。 その一環でしょうか、「南御堂シアター」の第一回として 「石巻市立湊小学校避難所」という映画が放映されました。 無料のイベントですが、事前に申し込みが必要です。 毎日前を通る南御堂の前に宣伝の看板が立てかけられていましたので、 早速申し込んで見ることができました。 まずは、浪江町で語り部をなさっていたという吉川裕子さんが登場。 浪江町で震災当時何度も「ここへ」「あそこへ」と 訳も聞かされないまま避難を強いられたそうです。 今思えば、原発からの放射能が広がって行く方向に逃げたそうで、 「内部被曝はしてるわな」と福島弁でお話されました。 現在は大阪市に住む娘さんの勧めで堺市の公営住宅に避難され、 震災の語り部として活動されているとのことです。 福島から避難してきた人たちは、 家のドアに汚物を下げられるなどの嫌がらせにもあっている、 「早く帰れといわんばかりだ」とも「放射能は伝染りませんから。キスしても大丈夫ですよ」と 冗談を交えて訴える姿も痛ましい思いがしました。 会場では驚きと、非難の声だと思いますが「えええ!」「そんな!」という声が上がりました。 福島弁でユーモアを交えて震災の実際をお話ししている姿に頭が下がります。 また、映画の中ではボランティア団体が歌を歌っている場面で ウサギ追いし・・・「故郷」が流れると 「故郷は故郷がある人がふるさとを思って歌う歌で、 ふるさとがなくなった私たちによく歌うよね!」という厳しい意見も聞かれました。 確かに震災から3〜4ヶ月の段階で「ふるさと」は厳しいですね。 被災者の本音だと思いました。 押し付けのボランティアにならない取り組みが必要だと思いました。 しかし、映画は監督さんの「暗いものにはしたくなかった」というお言葉どおり、 笑いが随所にあり、人々の明るさに驚きます。 4月21日〜10月11日に避難所が閉鎖されるまで、そこに泊まりこみ、 避難者に寄り添いながらカメラを回し続けた監督の思いは確実に伝わってきました。映画『石巻市立湊小学校避難所』...

映画「一枚のハガキ」南御堂シアターにて
今朝の御堂筋の銀杏です。 まだ、まだですが、色づく前に散らないかと少し心配です。 御堂筋に銀杏並木 さて、5日月曜日、南御堂シアターに行ってきました。 第2弾は 新藤兼人監督の最後の映画「一枚のハガキ」でした。 監督の次男でこの映画のプロデューサーの新藤次郎さんが映画の前にお話されました。 監督は4月22日に100歳になって、最後は老衰で今年5月に亡くなられました。 監督の経歴をはじめ色々なエピソードを交えて興味深いお話が聞けました。 その後、この日のために撮られた大竹しのぶさんからのビデオメッセージが流れました。 監督は実体験を映画にしていることが多く、私小説ならぬ「私映画」と言われるのだそうです。 一枚のハガキも戦争から復員してきた経験が大部分を占めているとか。 若い時に「世界戯曲全集」(48巻?)を読破し、シナリオライターとして活躍されたそうですが、なるほど、この映画もまるで舞台を見ているようでした。 舞台にしたら面白いかもしれないと思いました。 大竹しのぶ、豊川悦司、六平直政、大杉漣、柄本明などそうそうたる俳優陣で見ごたえがありました。 「戦争はまだ終わってない!」と叫ぶ豊川悦司 「戦争がみんな奪った!」と叫ぶ大竹しのぶ、 100歳を迎える監督が最後に選んだテーマです。 映画に登場する人はごく普通に生活している人々で、私でもあるんですね。たぶん。 戦争はどこか特別のところで、特別の人たちがしていたわけではなく、 今この瞬間も目の前にいる人の問題なんだと思いました。 ********** 一枚のハガキ 「今日はお祭りですが あなたがいらっしゃらないので 何の風情もありません。 友子」 ************* 監督のお墓は京都にあるそうです。 妻であり、同士であった乙羽信子さんとともに建てた墓には新藤さんが「天」という字を書いた。 「天という字は二人と書く」からだ。 どこまでも女性を愛する監督さんです。...
映画「一枚のハガキ」南御堂シアターにて
今朝の御堂筋の銀杏です。 まだ、まだですが、色づく前に散らないかと少し心配です。 御堂筋に銀杏並木 さて、5日月曜日、南御堂シアターに行ってきました。 第2弾は 新藤兼人監督の最後の映画「一枚のハガキ」でした。 監督の次男でこの映画のプロデューサーの新藤次郎さんが映画の前にお話されました。 監督は4月22日に100歳になって、最後は老衰で今年5月に亡くなられました。 監督の経歴をはじめ色々なエピソードを交えて興味深いお話が聞けました。 その後、この日のために撮られた大竹しのぶさんからのビデオメッセージが流れました。 監督は実体験を映画にしていることが多く、私小説ならぬ「私映画」と言われるのだそうです。 一枚のハガキも戦争から復員してきた経験が大部分を占めているとか。 若い時に「世界戯曲全集」(48巻?)を読破し、シナリオライターとして活躍されたそうですが、なるほど、この映画もまるで舞台を見ているようでした。 舞台にしたら面白いかもしれないと思いました。 大竹しのぶ、豊川悦司、六平直政、大杉漣、柄本明などそうそうたる俳優陣で見ごたえがありました。 「戦争はまだ終わってない!」と叫ぶ豊川悦司 「戦争がみんな奪った!」と叫ぶ大竹しのぶ、 100歳を迎える監督が最後に選んだテーマです。 映画に登場する人はごく普通に生活している人々で、私でもあるんですね。たぶん。 戦争はどこか特別のところで、特別の人たちがしていたわけではなく、 今この瞬間も目の前にいる人の問題なんだと思いました。 ********** 一枚のハガキ 「今日はお祭りですが あなたがいらっしゃらないので 何の風情もありません。 友子」 ************* 監督のお墓は京都にあるそうです。 妻であり、同士であった乙羽信子さんとともに建てた墓には新藤さんが「天」という字を書いた。 「天という字は二人と書く」からだ。 どこまでも女性を愛する監督さんです。...
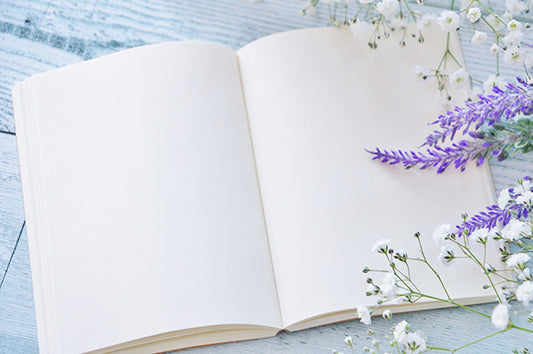
エンディングノートは必要ない!
故・金子哲雄氏が妻に託した“引き継ぎ”とは?『死後のプロデュース』(金子稚子・著)を発刊 残す人も残される人も心に留めたい「悲しみすぎない」ためのヒント。 金子さんが亡くなられた時には完璧な終活が話題になりましたが、残された遺族とくに奥さんの立場で書かれているこの書籍は重みがあります。昨今の終活ブームに、一石を投じる事になるのでしょうか? 昨年10月に肺カルチノイドで亡くなった、流通ジャーナリストとして活躍していた金子哲雄氏。その妻で編集者の金子稚子(かねこ・わかこ)氏が、その出逢い・結婚にいたるまで、そして病気が判明してからの死の準備と金子夫妻がおこなった「引き継ぎ」について語ります。 金子哲雄氏が、死の準備に積極的に取り組んだことは、当時報道もされて広く知られています。葬儀をイベントと捉え、病床で葬儀会社の人と打ち合わせをし、会葬礼状も自分でつくり、葬儀に限らず、生前にさまざまなことを稚子氏に頼んでいました。 そんな用意周到な哲雄氏ですが、エンディングノートは残していません。なぜなら、時間をかけて、妻・稚子氏に十分な引き継ぎをしていたからです。 結果的に稚子氏は、その引き継ぎによって、残された者たちが「悲しみすぎない」生活を送れることを実感します。大切な人を亡くした、厳しい悲しみは決して癒されるものでも、乗り越えるものでもないのかもしれない。しかしこの時、大きな支えになるのが、この「引き継ぎ」ではないか、という考えに至ります。 さらには、在宅医療やスピリチュアルペインについて、また死後も続く関係のことなど、あらゆるケースと情報を織り交ぜて、“死後をプロデュースする”ことについて解説します。 株式会社PHP研究所(京都市南区・代表取締役社長 清水卓智)は、2013年7月16日、PHP新書『死後のプロデュース』(金子稚子・著) 悲しみは悲しみとして抱えたままでも、それはそれとして次に進むために……残す人も残される人も参考にしたい、生と死を冷静に見つめる一冊です。 ※本書の一部は、こちらから試し読みできます。 http://shuchi.php.co.jp/article/1532 【目次】 第1章 金子哲雄の死の準備 第2章 引き継げる関係をつくっておく 第3章 「引き継ぎ」から生まれること 第4章 「死」とは何か? 第5章 「引き継ぎ」のすすめ 【著者プロフィール】 金子稚子[かねこ・わかこ] 1967年、静岡県清水市(現:静岡市清水区)生まれ。静岡女子短期大学(現:静岡県立大学短期大学部)卒業。雑誌・書籍の編集者、広告制作ディレクター。 2012年10月に亡くなった流通ジャーナリスト金子哲雄の妻。夫の死後、出版された金子哲雄著『僕の死に方 エンディングダイアリー500日』(小学館)でも執筆ならびに編集制作補助に携わった。夫の“宿題”を引き継ぎ、誰もがいつかは必ず迎える「その時」のために、情報提供と心のサポートを行うべく活動を始める。一般社団法人日本医療コーディネーター協会顧問。 【商品情報】 ■発売日:2013年7月16日 ■判型:新書判並製...
エンディングノートは必要ない!
故・金子哲雄氏が妻に託した“引き継ぎ”とは?『死後のプロデュース』(金子稚子・著)を発刊 残す人も残される人も心に留めたい「悲しみすぎない」ためのヒント。 金子さんが亡くなられた時には完璧な終活が話題になりましたが、残された遺族とくに奥さんの立場で書かれているこの書籍は重みがあります。昨今の終活ブームに、一石を投じる事になるのでしょうか? 昨年10月に肺カルチノイドで亡くなった、流通ジャーナリストとして活躍していた金子哲雄氏。その妻で編集者の金子稚子(かねこ・わかこ)氏が、その出逢い・結婚にいたるまで、そして病気が判明してからの死の準備と金子夫妻がおこなった「引き継ぎ」について語ります。 金子哲雄氏が、死の準備に積極的に取り組んだことは、当時報道もされて広く知られています。葬儀をイベントと捉え、病床で葬儀会社の人と打ち合わせをし、会葬礼状も自分でつくり、葬儀に限らず、生前にさまざまなことを稚子氏に頼んでいました。 そんな用意周到な哲雄氏ですが、エンディングノートは残していません。なぜなら、時間をかけて、妻・稚子氏に十分な引き継ぎをしていたからです。 結果的に稚子氏は、その引き継ぎによって、残された者たちが「悲しみすぎない」生活を送れることを実感します。大切な人を亡くした、厳しい悲しみは決して癒されるものでも、乗り越えるものでもないのかもしれない。しかしこの時、大きな支えになるのが、この「引き継ぎ」ではないか、という考えに至ります。 さらには、在宅医療やスピリチュアルペインについて、また死後も続く関係のことなど、あらゆるケースと情報を織り交ぜて、“死後をプロデュースする”ことについて解説します。 株式会社PHP研究所(京都市南区・代表取締役社長 清水卓智)は、2013年7月16日、PHP新書『死後のプロデュース』(金子稚子・著) 悲しみは悲しみとして抱えたままでも、それはそれとして次に進むために……残す人も残される人も参考にしたい、生と死を冷静に見つめる一冊です。 ※本書の一部は、こちらから試し読みできます。 http://shuchi.php.co.jp/article/1532 【目次】 第1章 金子哲雄の死の準備 第2章 引き継げる関係をつくっておく 第3章 「引き継ぎ」から生まれること 第4章 「死」とは何か? 第5章 「引き継ぎ」のすすめ 【著者プロフィール】 金子稚子[かねこ・わかこ] 1967年、静岡県清水市(現:静岡市清水区)生まれ。静岡女子短期大学(現:静岡県立大学短期大学部)卒業。雑誌・書籍の編集者、広告制作ディレクター。 2012年10月に亡くなった流通ジャーナリスト金子哲雄の妻。夫の死後、出版された金子哲雄著『僕の死に方 エンディングダイアリー500日』(小学館)でも執筆ならびに編集制作補助に携わった。夫の“宿題”を引き継ぎ、誰もがいつかは必ず迎える「その時」のために、情報提供と心のサポートを行うべく活動を始める。一般社団法人日本医療コーディネーター協会顧問。 【商品情報】 ■発売日:2013年7月16日 ■判型:新書判並製...

父のお骨1
退職して8年、脳梗塞ではじめて倒れてから10年、昨年5月父は76歳を目前に亡くなりました。 病気が長かったので、母をはじめ家族はみな心の準備はできていたと思います。父親とあまり仲良くなかった私はもちろん。 しかし、斎場で待つ時間が長かったこと、出てきた彼の変わり果てた姿、むごいですよね。 遺体を焼いてお骨で遺族に見せるなんて。 この世のものでなくなったんだと、存在自体が否定されたんだと、涙がこぼれ落ちました。 その瞬間が私にとっては、一番悲しかったです。今でも思い出すと涙が出ます。 メモリアル商品を取り扱っていますから、母と相談して、お骨を少しだけ身近において置けるものとして、陶器の小さなつぼを選びました。 つぼの下に台がほしいね、ということになり、敷物でもいいなと話をしていたら、母が「ネクタイがたくさんあるのよ。あれでできないかしら」と言い出しました。 18歳で家を出た私にとって、父の背広姿として記憶に残るのは、黒々とした髪の毛をポマードでオールバックにして、笑っている父、ネクタイを締めていたことすらはっきりしません。 晩年どんなネクタイを締めていたのか? 母が両手に持ってきたネクタイを見ると、どれも安物で、使い古されていました。 仕事柄靴にはうるさくて、銀座ヨシノヤの靴代を貧乏な家計から捻出するのがつらかったと母は言っていましたが、服やネクタイはどうやら安物だったようです。 普段は、ボタン付けくらいしかしない私が、珍しく針と糸を持ってチャレンジです。 「ネクタイってバイアスなんだ!伸びてくるし、切るのも縫うのもしにくいなあ!」母は横で呆れ顔。 縫い目は曲がりましたが、何とか一応敷物らしくはなりました。 ミニ骨つぼを販売していると、やはり、敷物はついていないのですか? というお問合せを時々いただきます。 これ以降、そんなお客様には、是非故人様のお洋服やネクタイの生地でお作りになってくださいと申し上げることになりました。 へたくそでも、ひと針ひと針縫ってみてください。ご家族とお話しながら、思い出しながら。 母とごちゃごちゃいいながら、縫ったこと、それがまた父との思い出になりました。
父のお骨1
退職して8年、脳梗塞ではじめて倒れてから10年、昨年5月父は76歳を目前に亡くなりました。 病気が長かったので、母をはじめ家族はみな心の準備はできていたと思います。父親とあまり仲良くなかった私はもちろん。 しかし、斎場で待つ時間が長かったこと、出てきた彼の変わり果てた姿、むごいですよね。 遺体を焼いてお骨で遺族に見せるなんて。 この世のものでなくなったんだと、存在自体が否定されたんだと、涙がこぼれ落ちました。 その瞬間が私にとっては、一番悲しかったです。今でも思い出すと涙が出ます。 メモリアル商品を取り扱っていますから、母と相談して、お骨を少しだけ身近において置けるものとして、陶器の小さなつぼを選びました。 つぼの下に台がほしいね、ということになり、敷物でもいいなと話をしていたら、母が「ネクタイがたくさんあるのよ。あれでできないかしら」と言い出しました。 18歳で家を出た私にとって、父の背広姿として記憶に残るのは、黒々とした髪の毛をポマードでオールバックにして、笑っている父、ネクタイを締めていたことすらはっきりしません。 晩年どんなネクタイを締めていたのか? 母が両手に持ってきたネクタイを見ると、どれも安物で、使い古されていました。 仕事柄靴にはうるさくて、銀座ヨシノヤの靴代を貧乏な家計から捻出するのがつらかったと母は言っていましたが、服やネクタイはどうやら安物だったようです。 普段は、ボタン付けくらいしかしない私が、珍しく針と糸を持ってチャレンジです。 「ネクタイってバイアスなんだ!伸びてくるし、切るのも縫うのもしにくいなあ!」母は横で呆れ顔。 縫い目は曲がりましたが、何とか一応敷物らしくはなりました。 ミニ骨つぼを販売していると、やはり、敷物はついていないのですか? というお問合せを時々いただきます。 これ以降、そんなお客様には、是非故人様のお洋服やネクタイの生地でお作りになってくださいと申し上げることになりました。 へたくそでも、ひと針ひと針縫ってみてください。ご家族とお話しながら、思い出しながら。 母とごちゃごちゃいいながら、縫ったこと、それがまた父との思い出になりました。

異国の丘
「異国の丘」という劇団四季のミュージカルがあるのだそうです。 先日新聞で、「引き揚げ港」であった舞鶴での公演が報道されていました。 「引き揚げ」といって通じるのは、私の世代まででしょうか? たぶん私の子どもの世代にとっては死語となってしまっているのではないでしょうか。 「引き揚げ」で、6年前はじめて舞鶴での散骨をお手伝いしたときのことを思い出しました。 ご主人の散骨をされたタエさんは、赤いコートを羽織ったかわいらしいおばあちゃんでした。 戦時中を満州で過ごされ、ずいぶんとハイカラな女学生だったそうです。 戦後、ご主人様と必死の思いで引き上げてこられたのが、ここ舞鶴だったそうです。子どもさんのない彼女は、親戚の方と、お弟子さん(お花の先生)だという二人の女性とともにはるばるやってこられ、感慨深げに船べりにたたずんでおられた姿は今も忘れられません。 散骨を終わって、引き揚げ記念館にお連れしたり、ご一緒にランチをしたり、すっかり仲良くさせていただきました。帰られてから、お菓子を送っていただいたり、それからは毎年年賀状もいただくようになりました。 タエさんの地元でも公演があることが分かったので、「異国の丘」のチケットを送ることにしました。 シベリア抑留の話だそうですが、同じ時代を生き抜いた彼女にも楽しんで(と、いうにはあまりにつらい経験だったのかもしれませんが)いただければと思います。 ハイカラなタエさんには、きっとミュージカルの踊りも歌も楽しんでいただけると思うのです。 「引き揚げ」と一言で言ってしまうにはあまりに多くの人々の「悲しみ」や「苦悩」、「怒り」や「慟哭」、戦争は終戦の日で終わったのではないことを、子どもたちの世代に伝えていきたいと思います。 紅葉狩りのついでに、舞鶴引揚記念館にお立ち寄りください。
異国の丘
「異国の丘」という劇団四季のミュージカルがあるのだそうです。 先日新聞で、「引き揚げ港」であった舞鶴での公演が報道されていました。 「引き揚げ」といって通じるのは、私の世代まででしょうか? たぶん私の子どもの世代にとっては死語となってしまっているのではないでしょうか。 「引き揚げ」で、6年前はじめて舞鶴での散骨をお手伝いしたときのことを思い出しました。 ご主人の散骨をされたタエさんは、赤いコートを羽織ったかわいらしいおばあちゃんでした。 戦時中を満州で過ごされ、ずいぶんとハイカラな女学生だったそうです。 戦後、ご主人様と必死の思いで引き上げてこられたのが、ここ舞鶴だったそうです。子どもさんのない彼女は、親戚の方と、お弟子さん(お花の先生)だという二人の女性とともにはるばるやってこられ、感慨深げに船べりにたたずんでおられた姿は今も忘れられません。 散骨を終わって、引き揚げ記念館にお連れしたり、ご一緒にランチをしたり、すっかり仲良くさせていただきました。帰られてから、お菓子を送っていただいたり、それからは毎年年賀状もいただくようになりました。 タエさんの地元でも公演があることが分かったので、「異国の丘」のチケットを送ることにしました。 シベリア抑留の話だそうですが、同じ時代を生き抜いた彼女にも楽しんで(と、いうにはあまりにつらい経験だったのかもしれませんが)いただければと思います。 ハイカラなタエさんには、きっとミュージカルの踊りも歌も楽しんでいただけると思うのです。 「引き揚げ」と一言で言ってしまうにはあまりに多くの人々の「悲しみ」や「苦悩」、「怒り」や「慟哭」、戦争は終戦の日で終わったのではないことを、子どもたちの世代に伝えていきたいと思います。 紅葉狩りのついでに、舞鶴引揚記念館にお立ち寄りください。










